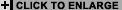第98話 『Culture Club in Japan 2016』
カルチャークラブが再結成して来日コンサートをする、というニュースを5月に聞いた。確か彼らの最後の日本公演は2000年だったか、僕はNHKホールに一人で見に行った記憶がある。その時は何人かの知り合いや、かつて1983年とか84年だったか人気絶頂時に、いつも会場に来ていた当時の10代の女の子たちの顔も見受けられた。皆公平に十数年経っているのだが、好きなバンドを聞きにくるファンの表情は、時計を何周も逆回しした如くに若くなる。人間は、心から愛するものに触れる時は、一様にエイジレスになるのだと思う。そのNHKホールでのことだ。次の曲紹介のMCを聞いた瞬間、曲紹介を待たずにすぐにこの曲だと容易に推察出来た場面があった。ジョージのMCはこうだった。「僕がこの曲を書いたのは何年も前の若い頃で、書いた時には気づかなかったことが、今はちゃんと分かるんだ!」そして歌い出した曲が僕の予想通りの“ビクティムズ”だった。このスローなバラードを何度聞いても飽きることがない。曲の途中にブレイクがあって、次にドラムのソロが入るところなど、いつか僕もドラマーになってその部分だけでも叩いてみたいと思う程だ。
この2000年の来日の時は、僕は楽屋に行く手筈を踏んでなく、ジョージに会うこともなく会場を後にした。NHKホールから渋谷まで、公園通りの坂道を下りながら、僕が最後に彼らに会ったのはいつだろうかと思い返してみた。確かロンドンで1985年とかではなかっただろうか。
あれから16年が経った今年の6月にカルチャークラブのコンサートがあるという。コンサートに行って彼らの姿を見てみたい、ジョージに今一度会って一つだけ尋ねてみたいことがどうしてもあった。楽しみなような、不安なような、どちらともつかない、今まで体験したことのない気分だった。とりあえず6月21日のZep Tokyoのチケットを買った。
あれは1979年、ロンドンがもう冬支度を始めた頃の季節だったと思う。北海道より北にあるイギリスのロンドンは、夏が終わりに近づくと、まるで急坂をころがり降りるような速さで冬がやってくる。パンクロックが流行りだして3年目、早くもイギリスの若者は次のムーブメントを敏感に感じ始めていた。モヒカンと革ジャンに身を包んだパンクロッカーが闊歩していたキングスロードを始めとする、ロンドンのストリートには、それまでの数年とはどこか違う雰囲気を持った若者が混ざり始めていた。友人のフランキーが僕を、最先端の若者が集っているというクラブに連れて行ってくれた。コベントガーデンからホルボーンに向かって歩いて行くと、そのクラブはあった。BLITZ(ブリッツ)という、昼間は変哲もないただのワインバーが、木曜日の夜になると空気が一変するのだという。入り口でスティーブという青年を紹介され、僕は恐る恐る中に入って行った。一階はそれ程広くないフロアーにバーカウンターがあり、地下に降りると、そこは踊り場になっていた。小さな丸いテーブルと椅子が幾つかあり、若者が喋ったり、お酒を飲んだり、踊ったりしていた。流れている曲は主にデビッド・ボウイとか、パンクとは違ったお洒落な曲の数々だった。僕が一番驚いて逃げ腰になったのが、フロアーにひしめく彼らのメイクや衣装だった。およそ今まで見たこともない様相を呈していた。まるで宇宙人ではないか!赤や緑、青のライトにかすかに浮かび上がる彼らの姿は、あえて例えれば、怪しい深海魚の薄暗い水槽の底を覗き込んだかのような異様さであった。
一眼レフにストロボを付け、近くにいた一番可愛らしい、顔を白く塗った女の子の二人連れに向けてシャッターを切った。どんな反応が返って来るのか、皆目見当がつかない混乱の中だった。
「Did you get a nice picture of us?」
何とその声は。驚いたことに、少し高めではあっても男の声だったのである。
でもその声の主は、軽やかに笑っていて、とても嬉しそうで、僕はこの場所で初めて安心した。このクラブにいたのは、宇宙人でも深海魚でもなく、紛れもない最先端にいるイギリスの若者たちだったのである。
「I’m George!」
これがこのブリッツでの初めての会話で、思えば、ジョージとの最初の出会いであった。彼はこの時19歳になるかならないかの年齢だった。フランキーの話によれば、彼らはここブリッツに毎週木曜日の夜、「Bowie Night」というコンセプトで集まってくるが、それ以前には、もっとソーホー寄りのビリーズという店に集まり始めたということだった。ブリッツの木曜日がレギュラーになっても、木曜日以外の夜はカフェ・ドゥ ・パリ や ル・キルトといったクラブに行くと、ジョージや、その他の彼らの姿を見ることが出来た。その度に僕は先ずジョージにカメラを向けた。いつも彼は僕にレンズを向けられても愛想の良い笑顔を向けてくれるからだ。その後、何ヶ月が経つうちにエンバシー、グレート・ウオール、クラブ・ オブ・ヒーローズと彼らの領土は広がっていった。
さて、その頃の僕は、とにかく貧乏で毎日3食のまともな食事は諦めていた。運良くロンドンにある日本食レストラン「花車」のお寿司屋さんの武内さんやママのヒロミさんを頼り、夕方になるとレストランにお邪魔し、従業員と一緒にまかないのご飯を食べさせてもらうこともしばしばであった。家賃を捻出するのがさらに困難で、友人宅に居候させてもらうことが通常のパターンだった。そのうちの一つ、36番地グッチストリートの最上階のフラットに居候していたことがある。若い劇作家ジョニーと革の服を作るジーンのカップルが住むフロアーだった。かなり古い建物で、室内は手入れもされてなく、絨毯が敷いてない木の床材が丸出しの貧相な場所だったが、小さい部屋が3つ4つあっただろうか。ロンドンの中心街のこのフラットは、ジョニーの母親である有名な劇作家パム・ジェムスの持ち物だった。しばらくの後、あのジョージがやはり貧乏でか、ジーンを頼って同じフロアーに引っ越して来たのだった。狭い彼の部屋には僕と同じで、マットレスが床に直に置かれ、小さな机の上は化粧品が散乱していた。奇妙な4人の生活が始まったのであるが、彼はジーンに気を遣ってか家の中では物静かで、外泊することも多かった。ある晩、夜までジョージが帰ってこないので、彼は外泊だろうと予想して、僕はジョージの床に置かれたベッドに無断で一晩寝ることにした。何故かというと彼のかけ布団の方が、自分のよりまだ厚く暖かそうだったからだ。僕の薄っぺらな毛布一枚では、ロンドンの冬には十分ではなかったのである。
寝入ってた深夜に、枕元の電話がルーッルーッとなった。ジョージの使っている部屋には電話が引いてあったのだ。すぐに電話に出るとジョージだった。僕があまりにもすぐに電話に出たので彼はすぐに気づいてしまった。
探るような声だった。「Are you in my bed?? 僕のベッドに寝ているのかい?」ばれてしまったのだから、嘘をついてもしょうがない。僕は正直に謝ることにした。「そうだよ、ごめんね、君のベッドの方が暖かかったから、、。」そして「Do you mind?」と続けた。
駄目だ!と言われれば、謝ってすぐに自分のベッドに戻ろうと思った。
1〜2秒の沈黙があった。いくら余裕のないサバイバル的な生活をしている僕であっても、やはりギリギリの生活をしているジョージに甘えることは許されないであろう。親し仲にも礼儀ありである。そして僕はごく普通のストレートな人間であるし、彼のプライバシーに深く入り込むことはあり得ないのだ。さらにジョージにしてみれば、僕はクラブでよく見かける日本人のカメラマンということでしかなく、彼にとって、僕に必要以上に親切にするメリットは何もないのだ。しかし、確信に満ちた明るい声が返ってきた。
「No, you can use my bed!」
僕は、彼に失礼なことをしたと深く反省しながら、彼の暖かい言葉を心に染み込ませた。
その時電話の向こうのジョージはロンドンから約1時間北の街、バーミンガムにいるという。ジョージの友達のKに用事があるのだけれど、電話代がないからKにバーミンガムへ電話するように言って欲しいということだった。
「わかった、直ぐにKに電話して、君に連絡するように言うから。。。」
そう言って電話を切った。Kにジョージのことを伝えると、その晩僕はいつもより暖かい布団で眠ることが出来たのだった。
その当時の僕の収入は、たまにある日本のカルチャー誌のロンドン取材や、シャーリーという女性が組織していたイギリス人と僕を含めた数名の若い写真家が属しているZENONという写真事務所から、幾ばくかの仕事しかなかった。とても家賃など払えない状況だった。日本の音楽誌の仕事に有り付つける以前の僕は、イギリス人や日本人の知り合いの貴重な親切心の上にやっと成り立っていた。
ある日、日本人の友人である自称現代美術家のテツが僕に言った。テツはジーンの元のボーイフレンドだった。「この前さ、ハービーが今住んでいるジーンの所へ久々に行ったんだけどさ、あそこにジョージがいるやんけ!俺がちょうど真夜中にいた時にさ、ジョージが帰って来てさ、半分泣きべそかいてるわけ。どうした?って聞いたら、街で何人かから唾をかけられて散々罵られたんだって。
あんな格好しているからしょうがないんだろうけど、落ち込んでいたぞ!」
確かにロンドンでは女型は奇異な目で見られ、いじめられるのだろうと想像した。いつの時代にも、新しいものを始める時には先駆者は必ずと言っていい程、保守的な人間から攻撃されたのだ。たった数年前のパンクロックだって、テッズとかの昔の勢力との争いがキングスロードではよく見られたものだ。
思うにジョージがロンドンに住んでいた日本人たちに人当たりが良かったのは、日本には歌舞伎という男性が女型を演じるという素晴らしい文化が存在することを知っていたからだ。「日本の歌舞伎では、女型が認められているんだろう?」と聞かれたことがあった。幸いなことにジョージに会う3年前の1977年、日本から三代目市川猿之助さんが、初めての海外公演ということでロンドンにいらした。
その時の全工程の撮影を僕が依頼され、一週間を猿之助さんらと共に過ごしたという貴重な経験があったので、ジョージにも自信を持って歌舞伎の印象を伝えた。ジョージは日本の歌舞伎に、大げさに言えば、世間の冷たい目に屈しないための、いわば人生の拠り所を求めていたのだった。
あのジョージは将来、どんな人間になっていくのだろう。今はカーナビー・ストリートの洋服を売る露店の店で働いていたり、クラブのクローク係りをして生活している様だけど、もしかしたら洋服のデザイナーとか、小さなクラブをロンドンで始めるのだろうか。
ある日、日本人の友達の所で数泊した後、しばらく振りにグッチストリートに戻ると、先週ジョージはどこかへ引っ越して行ったという。かつて彼の部屋は派手な衣装や化粧品が散乱していたが、もはや無人の部屋は、あたかも役者の去った後の舞台の様に静まり返っていた。
それから何ヶ月か、それとも一年が経っただろうか。ジョージがコンサートをするのだという。その夜チャーリングクロス駅の地下のライブハウスに出かけた。「今日から僕はボーイ・ジョージさ!」と誇らしげに彼は、ドラマーのジョン、マイキー、ロイを僕に紹介してくれた。コンサートが始まるとノリの良い曲につられて満員の客は踊り出し、また独特のトゲとユーモアあるMCが大受けだった。素晴らしい舞台度胸だった。これがカルチャークラブの誕生した日だった。
実は数ヶ月前、マルコム・マクラレンがマネージメントしているバウワウというバンドの撮影に行った。ロンドンの北にあるホールだった。しかし、ボーカルのアナベラの年齢は弱冠16歳の少女で、深夜のコンサートには出演が法的に禁じられていた。そのアナベラの代わりにジョージがステージに出てきて数曲を歌ったのを目撃したことを思い出した。彼には歌う才能があったのだ。
瞬く間に彼らカルチャークラブの人気は、目覚ましい勢いで上昇していった。クラブやディスコでは頻繁に彼らの曲が流れていた。
その人気はたちまちに日本にも飛び火した。1983年だったか、カルチャークラブの初来日の時、そして次の日本ツアーにも僕は彼らと日本を周った。歌舞伎にも連れて行った。猿之助さんのロンドン公演の時に知り合った歌舞伎のカメラマン福田さんに頼んで、歌舞伎座の楽屋にジョージを連れて行った。あのフレンドリーなジョージが正座をしたまま固まっていた。
「もっと役者さんの近くに寄ってよ!」と彼を促しても、ちょこっと1センチだけ動くという有様で、あんなにかしこまった表情のジョージを初めて見たのだった。
2回目の来日の時だったか、京王プラザホテルから会場である武道館に向かうバスのなかで、新曲の歌詞の一部を日本語で歌いたいと突然言いだした。ふと考えついて「センソー ハンタイ!」と教えた。しかし、その夜の公演で彼は「センソー ヘンタイ!」と歌ってしまったのだった。
あれは日本でのことか、それともヨーロッパツアーの時だったか、ジョージはバスの後部座席で、彼の好きなミュージシャンの模写を披露してくれたことがあった。そこにいたのはジョンとバックミュージシャンのほんの数人しかいなかったが、ジュージを取り囲んでいた。
デビット・ボウイ、そしてジャパンのデビット・シルビアン、さらにもう一人は誰だったか。その歌の上手いこと。たちまち僕たちは彼の歌の世界に引きずり込まれてしまった。
調子に乗って僕がデビット・シルビアンの物真似を一章節だけ歌ってみた。その瞬間「ハービーは歌うのはやめた方がいいな!」とジョージにきっぱりと言われた。彼の瞬時の判断は正しかった。 僕は音楽を聴くのは大好きだが、演奏、歌唱能力は果てしなくゼロなのである。
僕が最後にジョージに会ったのはいつのことだろう。ひょっとしたら1985年とかのロンドンの何かの記者会見の時が最後だった気もする。
ここ2年程前に彼のツイッターを見つけたので、短いメッセージを送ったことがあった。「ジョージ、久しぶり、ハービーですが、憶えていますか。今は日本に住んでいます。また会えたらいいですね!」
する意外にもすぐに返事が届いたのである。「わおー、ハービー!何年も会ってないね、どうしているよ?日本で幸せなの?」最後の’Are you happy in Japan?’という一行がとても余韻として心に残った。人が幸せかどうかの確認作業は、思いやりがなくては生まれないものではないだろうか。
いつか、「僕は幸せだけど、君は幸せ?」そんな会話をジョージとしてみたいと思った。
その会話の可能性が、カルチャークラブの16年振りの来日によって、なんと31年振りに巡ってくるかも知れないのだ。
ツイッターで、「21日のコンサートには家族で行きます。」と知らせた。
もし会えたなら、ジョージの写真を何枚か渡したいと思いついた。選んだ写真はいずれもかつての古い写真だ。無名時代にクラブで踊っているジョージ、グッチストリートの部屋でベッドの中で寝ているジョージ、そして、デビュー直後にアルマ・ストリートに引っ越した先で撮った一枚。日本ツアーで新幹線の中のカットなどである。アルマ・ストリートで撮った写真は、今年になって初めてネガからプリントしたものだが、それ以外の写真は過去にジョージに見せたり、渡したしたことがあった。しかし、どれもジョージの原点が写っている写真だった。例えば、グッチ・ストリートでの一枚には、床に直に敷いたマットレスに寝ているジョージ、そして画面の右手にはジーンが「早く起きなさいよ!!」と強い口調でジョージに告げている姿が写っている。ジョージは叩き起こされたまま、ボーッと宙を見つめている。この時の居候という弱い立場でしかない自分を受け入れながら、将来の夢をぼんやりと夢想していたのだろうか。シャッター音が部屋に響くと、ジョージが、変なところを撮られてしまった戸惑いからか「Oh My Gossyu!」と小さく発した。この「Wake Up !」と題された写真は、僕のロンドンの写真集に載っているが、この写真を1983年か84年の来日の時に、宿泊していた京王プラザホテルでジョージに見せたことがあった。いわば彼にとって屈辱と言っていい瞬間の写真なので、彼は「こんな写真は見たくない!」と一蹴されることも覚悟していた。だが予想に反し、彼の反応は意外だった。写真を見るや彼は大声を上げて喜んでくれたのである。「わー、これがリアルな以前の僕の姿さ。昔は貧相に暮らしていたって言っただろう!僕の人生で最悪な時期だったよ。誰も信じてくれなかったけど、ハービーが撮ってくれていたこの写真が証明してるだろ!そして、ある冬の寒い夜、彼女はどこに行く当てもない僕を追い出したんだ!」。彼は周囲のメンバーやマネージャー一人一人に写真を見せて回ったのだ。
6月21日は、朝から嬉しいような、ナーバスな、興奮するような、かつて体験したことのない気分だった。夕方にZEP TOKYOに向かった。コンサートが始まった。会場の後部に関係者席として仕切られた一角で彼らを見守った、彼らの紡ぎ出す音のグルーブがこれ程までに心に響いてくるとは驚きだった。恐らく僕が今まで体験したコンサートの中でベストな一つだろう。お馴染みのヒット曲の数々が、より説得力と音楽の力で聴衆を包み込み、まるで違う曲の様に聞こえた。「あれっ この曲は何??」と思うと、あのヒット曲ではないか。
ステージ上での彼の動きも張り上げる高音の伸びも、若い頃とは少し違うのだけど、ジョージそのものだった。そこにはとてもソウルフルで、暖かく優しく、厚みがあって、強い何かがほとばしっていたのだ。何十年もの間、我々が気付けなかった彼らの本当の姿がそこにあったように思われた。名曲「ビクティムズ」を歌い上げた後だった。まっすぐな目を輝かしながら、心の全て開き、ジョージの全てを受け入れようと聞き入る日本のファンの姿をまじかに見たからだろう。「日本はベストだよ。 英語や日本語を通り越して、何年経っても音楽を通して繋がれる。日本は僕の精神的な故郷なんだ!」そして「泣きそう!」と日本語で加えたのである。彼のステージからのMCには、デビュー間もない頃から独特の棘とユーモアとフレンドリーさがある。そして何より言葉が正直なのだ。
どのタイミングでだったか、客席に知り合いを見つけると「あそこに懐かしい顔がいるよ、あれは◯◯さんだよね!?」そして、「今夜はここに、僕のベストフレンドのハービーも来ているだろう?ハービーはどこにいるのかな??」と名前も呼んでくれたのである。僕は会場の後方の暗い関係者席にいたので、手を振ったが彼の視界には入らなかった。
コンサートが終わると、日本のスタッフが呼びに来てくれた。2階席に行くと何人かの人々が楽屋に行くために待機していた。そこでかつてのロンドンで一緒に仕事をしていたライターの黒沢さんに再会した。彼女に会うのも20年以上振りだろうか。黒沢さんはカルチャークラブのPVに芸者の姿で出演している。当時のロンドンには音楽一筋の優れたライターの若い女の子たちがいた。ミコ・クロサワ。キム・ヤマカド、ユーコ・タカノ。。。こと音楽関係の仕事に関しては、こうした彼女たちが撮影の仕事を僕に次から次へと振ってくれたのである。そのお陰で僕は貧困から抜け出ることが出来たし、それにつれてイギリスや日本のレコード会社やバンドから直接仕事のオファーが来るようになった。言わば彼女たちは僕を貧困から救い出してくれた幸運の女神たちだった。
僕と黒沢さん、その他十数人が日本のスタッフに先導されて楽屋に向かった。楽屋の廊下は人混みで、コンサートが終了したことによる独特の高揚感が充満していた。ひときわ明るい表情のジョージが先方に見えるではないか。激太りとかドラッグだとかで世間を騒がせたが、そんなことは一切感じられない、あのロンドンや日本での初期の頃のジョージが、そのまま前方にいたのである。ブロンドの女性とハグをしているジョージの視界に、僕はカメラを持って入って行った。すると僕を見つけた瞬間、ジョージの目が僕を注視し、ゲストの背中に回された彼の右手の人差指が僕に向けられたのである。「そこにいるのはハービーじゃないか!!」という仕草だった。僕たちは31年振りのビッグハグをした。彼の大きく太い腕が僕の背中を包み込んだ。「元気だったかい?」そして持参した写真プリントを彼に一枚一枚見せながら渡した。驚いたことに初めて見せるアルマ・ストリートでのプリントを見るや、「I’ve never seen this picture before」と言って手に取ってそのプリントを眺めたのである。そして廊下の先にいる黒沢さんを呼んだ。ジョージは「Oh ! Miko!」と一層懐かしそうに彼女にハグをした。こういう場所での長い会話は他の人の迷惑になるもので禁物だ。僕は手短にかつてからの質問をジョージにした。「Are you happy in your life ?」すぐさま快活な答えが返ってきた。」「Yes ! of course I’m happy!!」この言葉を聞いて、そこにいた僕と黒沢さんとジョージの三人は、一様に互いに安心し合ったのだった。
ジョージはこのコンサートのアンコールで尊敬するデビッド・ボウイの「スターマン」を歌った。ジョージは想像するに10代の半ばでデビット・ボウイの楽曲やファッション、その姿に触れ人生観を変えた。大抵の保守的な世間は、新しいものが奇抜であればあるほど攻撃してくる。1980年頃であってもジョージは街で唾をかけられたのだから、デビッド・ボウイが奇抜なスタイルを始めた時、とりわけ世間に正しく認知される以前には、もっともっと激しい社会からの反発を受けていたのではないだろうか。彼らの歌声がハイトーンになった時、とても悲しい心の叫びを感じるのは、彼らが信念を守り、戦ってきた証ではないだろうか。過去を振り返れば、彼らの人生の中で、幸せと悲しみはどれ程の割合で混ざり合っているのだろうか。少なくともこの日のジョージは、紆余曲折がおおいにあったにせよそれを乗り越え、こうして日本に囲まれ、心の底から幸せそうだった。