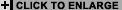|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 > 第55話 『暖かなギャラリー』 
第55話 『 暖かなギャラリー 』僕の家から歩いて15分位で、東京都写真美術館に行ける。ちょうど良い散歩の距離なので、目黒川沿いを歩いてプラプラと歩く。僕の胸には大抵ライカのM3がぶら下がっている。道すがら、これといった被写体に出会うとすかさずシャッターを数枚切る。何気ない日常の中に、時に、絵になる瞬間が潜んでいるものだ。 そして、都写美に着くと、じっくりと作品に向かい合う。気に入った写真展がある月は、同じ写真展を2度3度と眺める。これは写真家にとって必要なことで、良い作品から受ける力というものが、自分の元気、とか、この先写真を撮り続けるエネルギーになっていくのだ。しかし、都写美は権威があるというのか、厳かな空気が流れている。こういった雰囲気も良いのだろうが、僕の個人的な趣味で言えば、もっとアットホームな、暖かな雰囲気が都写美のどこかにあれば良いと思う。人が自由に笑顔で語り合える様な空気が流れるスペースがどこかの一角にあったら、もっと居心地が良くなるのに、と少し残念に思う。そういえば、都写美で、笑顔とか、暖かな人々の所作を見たことが無い。切符を切る女性達も、ショップの売り子さんも一様に無表情である。「入場者にいちいち愛敬を振りまいていたら体が持ちません!」ということなのだろうが、僕たち入場者は心のどこかで、この建物に入るや、ある種の冷たさとか孤独を感じるものだ。そして、入場者も次第に無表情になっていく。 去年、川崎市市民ミュージアムで、僕は250点を展示した大きな個展を開かせて頂いたが、このミュージアムも都写美と同じく大きな建物だった。僕は時間のある限り、週に2〜3回は車で市民ミュージアムに通った。せめて僕の個展会場は冷たい雰囲気を持たせたくなかったのだ。ショップや受付の女性達とも積極的に会話をした。その結果、もともとここにはぎすぎすした空気は流れていなっかたことも手伝い、最初は慣れぬ顔つきだった女性達は、僕の真意をくみ取り、笑顔を見せるようになり、そしてお客さんにも笑顔で接してくれるようになってきたのである。 会場の入り口に感想文を書くテーブルを用意してもらった僕は、そこをお客さんとの対話の場として活用した。僕の意を汲んだ受付の女性は、「今、あちらにいらっしゃるのが、ハービーさんですよ!」と入場するお客さんに教えて下さったりもした。僕は、僕で、一人ぽっちでいる寂しそうなお客さんには、自から話しかけ、リクエストがあればサインや記念写真に応じ、お客さんの声に耳を傾けた。 そこから生まれたのは、人が人と出会う、エキサイティングでポジティブで暖かな空気だった。 その甲斐あって、2カ月という長い開催期間は充実し、僕もスタッフも、僕に会えたお客さんも良い思い出を作ることが出来たのである。 2010年の一月から二月にかけ、目黒のブリッツと谷中のカフェ「藍い月」で写真展を開いた。ブリッツは土曜日、谷中は日曜日、仕事が無ければ午後2時過ぎから会場にいる日と定めていた。お陰で土日は両会場が人々で一杯だった。 僕の行動はお客さんと会話をするということだけには留まらない。お客さん同志を紹介し合うのだ。僕とは初対面の方々も当然沢山いるが、そんなことはお構いなく、お客さん同士が会話が出来る様なきっかけを、僕が作ってあげるのだ。 ある日曜日のことだった。谷中のカフェに行くと、店内は満席で熱気に満ちていた。店長の鈴木さんが、満面の笑みで、「今いるお客様全員がハービーさんの到着を待っていましたよ!」と告げた。店長はある女性のところに僕を連れて行き、「こちらのお客様は2時間もハービーさんの到着を待っていらっしゃいます」と説明した。僕はそのお客さんに深々と頭を下げた。 店の奥に長身の若い外国人がいた。彼はデジ一眼を持っている。話しかけると、「代官山17番地」以来、僕の写真のファンになってくれたとのことだった。日本にはもう8年も滞在していて、ある女子高で英語の先生をしているそうだ。彼の名前はダニエル。僕に会えてとても嬉しそうだった。固い握手を交わした。 そして、店の窓際のテーブルには別の外国人の男女がいた。聞くとロシアからの留学生で、一人は東大、もう一人は東京外大の学生だった。趣味で写真の学校にも通っている。何かの雑誌で僕の写真を見て、このカフェに来たのだそうだ。 僕は、ダニエルをこのテーブルに呼び、ロシア人学生を紹介した。ロシア人学生はポートフォリオを持っていて、テーブルの上に拡げた。そして日本人のお客さんもこのテーブルに呼び、そこに大きな輪が出来た。写真のクオリティーはまだまだなレベルだったが、一枚だけ良い写真があったのでそのページは褒めてあげた。 日本人のお客さんの中にもポートフォリオを持っていている方が何人かいた。そういえば、つい先日、FM横浜の小山薫堂さんの番組のゲストで呼ばれた際、「ポートフォリオを見ますよ!」と発言したのを思い出した。 元アンアンのデザインをやっていたという方がポートフォリオを持って来ていたので、皆で見ることになった。ヨーロッパで撮られたモノクロの写真は、どれも彼の世界観が見え、一味違う写真が多くあった。さすがにデザインを知っている人が撮った写真だった。 テーブルを囲んだ人々から、ページをめくる度に「おーっ」という声が漏れた。 ひとしきり写真を見た後、お客さん同志がメルアドを交換したり、記念写真を撮り合い始めた。そうこうしているとたちまち1〜2時間が過ぎてしまう。 お客さんが帰る時は、市民ミュージアムでもブリッツでも谷中でも、出来る限り、会場の外まで同行して、見送ることにしている。それが感謝の気持ちというものだし、礼儀というものだ。 今日はとても良いことがあったと言わんばかりに、皆、ニコニコして帰っていく。その表情を見るのがまた楽しい。 谷中での最終日、2月13日、午後5時から僕のトークショーが行われた。30名近い人達でカフェは一杯だった。このカフェ自慢の有機食材を使った料理とデザートが付いて、参加費が2000円というサービスだ。トークショーは終始和やかで、笑あり真面目な話ありで、参加して下さった方々は大いに盛り上がって下さった。 なんだか年末に行われる芸能人のディナーショーの様相である。取り敢えず8時30分に終演したが、直ちに帰る人はほとんどいない。ここで奥に座っていた男性が僕の所に来て、名刺を渡された。その方の名前に憶えがあった。 昨年の春頃だったろうか、朝日新聞の夕刊に写真家論の連載が9日間あった。毎日一人の写真家が登場し、写真との出会いや写真への切なる思い、そして興味深いエピソードを、誰にでも解り安い平易な文章で表してあった。僕はこの連載をとても気に入り、記事を切り抜いて保管していた。いつか僕もこうした記事に載るに値する写真家になりたいものだ、と密かに思ってたものだった。連載が9日で終わってしまったのがとても残念だった。もし、この連載が続き、一冊の単行本になったら、間違いなく、ベストな写真教育書になるだろうと僕は確信していた。記事の隅には、この記事の感想はこちらまで、という執筆者宛てのメルアドが記されていた。僕は、自分の感想を一度送った。「先輩写真家より過分のお言葉を頂き嬉しく思います」、という丁寧な返事が戻ってきた。僕の目の前に立っている方こそが、この連載を書かれた朝日新聞記者の相場さんだった。相場さんとこうして僕のトークショーで期せずして直接お会い出来ることになるとは、僕にとって凄く嬉しいことだった。 また、会場の空気は作家と来て下さった方々の精神性でがらりと変わるものだ。 「来て良かった」。そうしたワクワクした気持ちになれるギャラリーが一つでも増え、そして、そこから始まる人の輪がいくつも出来上がることを願うばかりである。 |