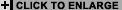|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 > 第57話 『ジャンルー・シーフのカフェ・トーク』 
第57話 『ジャンルー・シーフのカフェ・トーク』4月の18日、東京都写真美術館で僕のカフェ・トークがあった。僕の好きなフランスの写真家、ジャンルー・シーフの写真展の期間中のイベントだ。フィルムの粒子の際立つモノクロームの女性モードやファッション写真は、パリの洒落た空気感をまとい、独特の濃さとか深みがあって、とてもドラマティックに仕上げられている。初めて彼の写真に出会ったのは1977年、僕が27才の時だった。僕が所属していた[QUALITY OF LIFE]というイギリスの写真家グループのグループ展が6か月間のロンドンでの展示を終え、フランスのシャロン・シェル・ソーヌという小さな田舎街に再展示の招待された時のことだった。 この街は、フランスの写真術発明者として名高い、ニエプスの生まれた街で、彼の生家が残されている。またこの街には、彼にちなんだ素敵な写真ギャラリーがあるので有名だ。このギャラリーのライブラリーに日本の写真雑誌までもが置いてあり、ふと手にしたカメラ毎日にシーフの作品がモノクログラビアページに紹介されていた。 一瞥して僕はシーフの作品が好きになった。ニコンとライカを駆使していた彼の機材にも大いに共感を抱いた。多くは女性の下着姿を21ミリの広角レンズを駆使して大胆な構図に収めている。下着の生地、モデルの肌を覆う産毛などの質感が素晴らしい存在感を示している。普通、21ミリという超広角を使うと、歪曲が画面に出過ぎて不自然な不安定感が出てしまうのだが、シーフの作品には、その歪曲が適度な力となって見る者に迫ってくる。被写体との距離、被写体に対するレンズの傾け方の微妙なコントロールが巧みなのだろう。こうした写真を見ると超広角レンズを使いたくなる。ただ広く写すのではなく、また、歪曲を味方につける上手さに憧れを抱くのだ。 何ページかの、カメラ毎日のグラビアの中に、特に僕の歓心をかう一枚があった。白いウェディングドレスをまとった若い白人のモデルが左手に花束をだらっと下げ、階段の踊り場に立って左の横顔を見せている写真だ。壁にある四角い大きな窓から光が差し込んで、モデルの顔と衣装をさらに白く浮き上がらせている。さらに広角の適度な歪曲のため、10等身位の小顔に写っていて、その顔は笑うでもなく、暗くもなく、といって無表情ではなく、幼さを残しつつ品のある視線である。モノクロの美しさが100パーセント生かされ、そのシンプルさも手伝い、実に清楚な写真であった。 この一枚が、しばらくの間、小さな衝撃となって僕の胸に焼きついてはなれなかった。こうした、ただ惚れ込む写真に時として我々は出会うものだ。これは写真家として大切なことで、いつの日か僕もこうしたインパクトのある、こころに刺さる写真を取りたいという意欲につながるからだ。 4月から5月にかけて、このシーフの写真展が都写美で開催されている。 倉持さんとはもう20年以上の付き合いで、僕の写真を高く評価して下さっている方の一人だ。僕の写真集で1999年、ルクセンブルグ大使館から1000部限定で出版された、今では入手困難な[TIMELESS IN LUXEMBOURG]は、このG.I.P.がコーディネイトとディレクションをして下さった。 2009年9月、和江さんと、写真家の仕事について長電話したのを今も憶えている。 この2月の電話で和江さんは切りだした。 数日後、和江さんのから再び電話があった。 大切なのは、時代の流行とかに左右されることなく、、孤高になっても自分の信念を曲げずに、誠実に生き、自分なりの写真を根気良く撮り続けて行くことである。続けていればいつかもっと多くの人々のこころに届く日がくるのだ。シーフとて10年前に67才で他界するまで、広角レンズとモノクロームにこだわり、女性をモティーフにするという信念を通し続けたのである。 4月18日、午前10時からカフェ・トークの整理券が配られた。5分程で定員35枚分の券がほぼなくなった。午後4時半、倉持和江さんと僕の二人が席に着き、トークショーが1時間行われた。 彼は20代であった1950年代、ルポルタージュを主に活動していた。僕も20代だった1970年代、ロンドンから中近東に行った際のルポがフランスのガンマという写真エージェンシーを通し、アメリカやヨーロッパのグラフ誌に配信されていた。 一方僕は、シーフとは異なり、非演出にこだわり、また被写体を女性に限らず、広く街の人々の生きる中から、感動的な一瞬の素顔を切り取るスタイルを身に付けていった。 共通点は二人ともルポが出発点だということと、モノクロームにこだわっているということで、最大の相違点は、メインワークが彼の場合は演出写真で、僕の場合は非演出写真であるということだ。 カフェ・トークの際中にこんなことにも気が付いた。それは、彼の写真は、一部の風景写真を省くと、ほぼ例外なく縦位置であるということだ。僕も最近の写真は縦位置が断然多いが、横位置に比べ、縦位置写真には遠近感が強調され奥行感が増し、より立体的に画面が締まって見えるという特徴につながる。また、構図上、人物の上に広くスペースを開けると希望の印象が強まり、逆に人物の下方を見せると現実感が強くなるということにも触れた。 そんなことを徒然に話していると瞬く間に1時間が過ぎ、「そろそろ時間がなくなりました」、という声が学芸員からかかった。 美術館の入り口の大きなガラスの扉越しに外を見ると、目黒区三田の高台には大分長くなった春の光が注いでいた。 1977年、フランスの小さな田舎街のギャラリーで出会った、僕に衝撃」を与えた、純白のウエディングドレスをまとったあの写真のオリジナルプリントをそろそろ買いたいなと、ふと思うのであった。 |