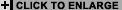|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 > 第62話 『コミュニケーション』 
第62話 『コミュニケーション』キヤノンギャラリーSでの写真展が始まった。40年も前の写真だから古くさくなるかと思ったが、懐かしさは服装などから感じさせるものの、人々の優しい表情はむしろ現在よりもっと強くて、新鮮な気もする。 確かに、40年前は個人情報保護法などはなく、自由に人々のスナップが街で出来た時代だった。公園で子供にカメラを向けると、本当に嬉しそうに、生き生きとした表情を返してくれた。会場に飾ってある一枚の中学生の女の子が、勉強机の前で雑誌を読んでいる写真がある。120センチ角の大きなプリントだ。この写真は、僕の自宅の向かい側にあった小さなアパートに住んでいた女の子を撮ったものだが、僕の気の向いた時、彼女のアパートに勝手に上がり込んで、お家の方に一礼して、「ヤー、元気、今日の宿題は?」などと話しながら数枚撮ったうちの一枚だ。しょっちゅう彼女と顔を合わせていた、近所の大学生と中学生という関係だったが、現在こんなことが出来るのだろうか、とふと思う。 ネガの何本かに、普天間基地のデモと書かれている。40年前から、一向に解決しない問題もあるし、知らず知らずのうちに、この40年間で、我々が失ってしまった「人を信じるこころ、とか、人を大切に思うこころ」が展示した写真の底流に見られるのではないだろうか。 この写真展のために、テーマ曲を書き下ろした。僕が詞の原案を書き、シンガー・ソングライターの入日 茜さんが、言葉を紡ぎ、作曲し、歌っている。ついこの前、スタジオでレコーディングをした。この入日さんの歌に出会ったのは、5年ほど、いやもっと前だったが、赤坂にあった、東京写真文化館で「ロンドン」の写真展を開いた時、初対面の彼女が「これ、あたしのCDなので聴いて下さい。」と手渡されたのがきっかけだった。
家に帰って聴いてみると、切々と歌う声と歌詞、時に切ないメロディーがことさらに印象的だった。その中に一曲、「レクイエムが聴こえる」という曲が素晴らしかった。
キヤノンの写真展用の新曲だが、僕が原案として提案した、「失ってしまった、人間を信じるこころ、♪」を「失ったのじゃない、忘れているだけ、人を信じるこころを、♪」と彼女は書き換えた。
10月2日のトークショーには、350名のお客さんが詰めかけて下さった。念のため多目に用意した400席が8割方埋まっていた。
この日から遡ってほぼ二週間前、広尾の小さなギャラリーで開かれた写真家の集まるあるパーティーに出席した。何人かの大御所と言われる写真家の先生が出席されていた。
いくら、僕が、先程書いたようなトークショーを開催しても、ここにいらっしゃる大御所と言われる先生方は、ほぼ100パーセントトークショーに参加されることはない。大御所と言われないまだ若い写真家も同じである。写真雑誌関係の方々も、評論家もまた同じである。僕が仮に、今の時代を揺るがすような問題作を発表するような作家であれば、事態は違うかも知れないが、僕は中庸な作風を通している写真家だ。従って、写真を生業としている方々の歓心を買うことはまずないのだ。トークショーは勿論のこと、写真展にだって数名の例外を除けば顔を出さないだろう。
「来月からキヤノンで個展を開かせていただきます。40年前の写真、僕が二十歳の時に撮った写真だけで構成しています。作風は今とほとんど変わっていません。0歳から15才くらいまで、病に伏せる冬の時代が続いて、二十歳になった頃、やっと春が来て、カメラを持って外に出たわけです。少年も少女も、学生運動も、キャンパスに行きかう学生も、日本に返還される前の沖縄も、街で見かける孫を抱いた老婆までもが、命を紡ぐ輝かしいものに見えたんです。それを無心に撮ったのが、キヤノンの個展です。
その甲斐あり、それまでスピーチを聴いているのかいないのかざわざわとしていた会場が、水を打ったかの様に,しーんと静まりかえって僕の話を聴いて下さった。大きな拍手が湧いた。お一人の先生が近寄って来て、「いやー、いい言葉だったね、感動したよ。君がこんなに話が上手くて、内容のあることを喋るなんて初めてしったよ!」 ものごとを発信する側、受け取る側、それぞれの真剣度で、折角目の前にあるのに見損なっているものが沢山あるのではないだろうか。 こう書くと、寂しい限りで希望の片りんもない様に思ってしまうが、それは間違えだ。 写真界の中にはちゃんと写真を見て下さって、正当な評価を下さる先生方が沢山いることをここで書かなくてはいけない。 先月出版した、僕のエッセイ集、「僕の虹 君の星」に登場する、奈良原一高氏は、「新人がデビューする時は、自分のスタイルを全面に押し出してくるもんだが、君にはそれが敢えてないのが清々しい」、また、東松照明氏は、「君はこのままの姿勢で写真を続ければ良いんだ」と仰っていただいた。いずれも1985年開催の渋谷パルコでのロンドンの写真展でのオープニングでのお二人の言葉である。 さて、9月24日、キヤノンの写真展の当日、夕方6時からギャラリーの3階でオープニングパーティーが開かれた。 乾杯の後、僕が挨拶をする番がやってきた。話した内容は、前回のパーティーとかぶることもあったが、「初志を貫くことの方が、人生の成功につながる確率が高いといわれている。褒めてもらうことも大切だが、嫌われることも覚悟の上で敢えて自分のために正直に苦言を呈して下れる人を身近に持っていることは財産だ。かつて、1980年初頭、イギリスのギターリスト、ゲイリー・ムーアのオフィシャル・カメラマンとして、全英ツアーに同行した僕だが、今年、20年振りに来日し、再会を果たした。そこで彼にギターリストとして、最も大切なことは?という僕の問いに、オリジナリティーを持つことだ、オリジナリティーを創るのに20年かかってしまったけれど、人は自分のギターを聴いてくれるようになった、という答えが返ってきた。天才といわれたゲイリーにしても20年かかったのだから、凡才の僕は一生、オリジナリティーを求めてもがくのだろう、、。」
ハービー・山口様 木之下 晃 写真界には、こんな素敵な先輩写真家が何人もいらっしゃるのである。 |