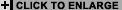第45話 『 写真家と被写体の資質 』
1980年代初頭のこと、世界的な人気を誇るアイルランド出身のバンド、U2を撮ったことがある。日本の音楽雑誌の表紙と巻頭の数ページを飾る仕事だった。ダブリンは古い歴史をのぞかせる独特の雰囲気のある街だった。郊外に車を走らせ高台にそびえる貴族の館がU2がリハーサル等の活動の拠点にしている有名な場所だ。僕はロンドンから小一時間かけて、この地へ向かったのだが、この館に着くや、そそくさと撮影のための準備にとりかかった。それを見たバンドのリーダーであるボノが軽く僕を制した。「慌てることはないさ。撮影の前に食事でもしないか、君のことを知りたいんだ。」 彼と僕とはこの時が初対面だった。ツアーをひかえた忙しい彼らだ。さっと撮って、すぐさまロンドンに引き返すことになるだろうと想像していた僕は、彼らの態度が意外だった。この館はダブリンの貴族の所有物で、U2の音楽に心酔するのにとどまらず、私財を提供してU2の活動を助けているのだ。こうしたアーティストと貴族との関係は日本では想像しにくい。シェフが豪華な昼食を料理してくれた。大きなテーブルに着き、思わぬ美味を楽しんだ。
食事の後、ボノは僕にいろいろなことを聞いてきた。なんでロンドンに住んでいるのか、日本はどんな国だ、どんな写真をとっているのか、、。30分位だっただろうか、僕は説明出来る限りの文化の違いや、僕自身の写真について彼と他のメンバーに語った。一つ二つ憶えているのが、日本の精神性を語る時、以心伝心ということを説明したことと、日本と西洋の良いところを結びつけたいと言ったことだ。写真に関しては、素顔の人間性を撮ることで社会を少しでもポジティブに出来たらといったことを彼らに語った。ボノは終始僕の目を見ながら真剣に僕の話に耳を傾けていた。彼の目の表情で彼がいかにシリアスかがうかがい知れた。そして笑顔に戻った彼は僕に言った。「君のことが少しでもわかったよ。さあ、写真を撮ろう、これからは君の時間だ。僕たちは君のリクエストにすべて応えるから何でも言ってくれないか!」
日本の音楽雑誌に掲載される記事や写真が彼らにとってどれ程重要なのか、取るに足りないものなのかはわからないが、撮影の直前に、初対面の写真家のことを知ってから撮影に臨むという彼らの真摯な態度が凄く嬉しかった。「これが世界に通じるバンドのやり方なのか、、。さすがだ!」 僕は、高台から見渡す限り、緑の起伏ある大地が続くその中で、澄んだ空気と青空を眺めながらカメラの前でポーズをとる彼らをこころゆくまで撮影したのである。
撮影といえば、つい先日ライカギャラリーで個展が始まった写真界の巨匠、エリオット・アーウィットのポートレイトを写真誌「PHaT PHOTO」の依頼で撮影した。彼の撮る犬にまつわる写真をはじめ、どこかユーモアのある作風は世界中の幅広いファンに受け入れられている。世界で最も愛されている写真家の一人だろう。彼に会うのは3度目だ。しかしすれ違っただけなので彼は僕のことを憶えていない。一度目は10年程前だった。日本写真家協会のイベントで彼を囲んでの座談会に出席したのだ。その中で僕は彼に質問をした。「エリオットさんは、スランプになったらどう立ち直るんですか?」 この質問に彼は「いつスランプから抜け出せるかは神のみぞ知るだけど、こんなことがあったんだ。昔撮ったネガを何年も経ってから見直すと、一枚とか二枚傑作が埋もれているんだよ。それを見つけると気分が良くなってスランプの時なんかに良いんじゃないかな。カルフォルニア・キッスという写真は、撮影から何年も経ってから偶然ネガを見つけたんだ。君もそうしたらいい。」
興味深い答だった。車のフェンダーに付けられた丸いバックミラーに、車内のキッスをしているカップルが写りこんでいる、このカルフォルニア・キッスと名付けられたモノクロの写真は、写真集の表紙にもなっている彼の傑作のひとつだ。以来僕もスランプの時は古いネガを見直すことにしている。そのお蔭で、joe with a rollupというクラッシュのジョー・ストラマーを撮った写真は正に、何年も前のネガを見直した時に見つけたものだ。いまやこの写真は僕の傑作の一枚になった。その証に、この春、人気グループEXILEの洋服ブランドが、この写真をプリントしたTシャツを製品にしたのだ。
さて、80歳のエリオットさんは約束の午前11時、銀座のライカギャラリーで僕と編集者の村田さんを待ちうけていた。お元気である。僕は名刺とロンドンの写真集を自己紹介の代わりにお渡しした。彼はぺラぺラとページをめくり、ありがとうと言った。その目にはかすかな微笑みがあった。ライカM3を僕が構えるのを見ると、自分も何台かのM3を持っていて、50ミリのレンズを主に使うということだった。そしてデジタルカメラは使わないそうだ。僕のカメラをきりっとした表情で見つめる彼に、「スマイルが欲しい」と言うと、「何か面白いことがないと、」と簡単にはいかなかった。「エリオットさんなら被写体に笑ってもらいたい時、どうするんですか?」と尋ねると「笛を吹くのさ」という答えだった。「今僕は笛を持っていないんですが」「どこかに売ってるだろう!写真を撮るっていう行為は良い時間の使い方だし、そんなに大そうなことじゃないんだよ。」 そんなやりとりをしながら36枚を撮りきった。翌日、暗室で8X10インチのサイズにプリントをすると、かっちりした目線もあったが大半は、僕のリクエスト通りの人の良さそうな優しい瞳がメガネの奥で微笑んでいた。
さて、その次の日、写真家の梅佳代さんと「じいちゃんさま」を編集したデザイナー祖父江慎さんに会った。祖父江さんとは昨年暮れ、寺山修司さんの写真集にまつわるトークショーでご一緒したが、梅佳代さんとは初対面だった。目の表情が生き生きしていて、女性としてとても凛凛しい魅力のある方だった。僕のライカを首にかけて、「このカメラって、ピントも露出も自分で合わせるんですよね!ほんとに専門家っていう感じ、、。」としきりに感心したり、彼女のキャノンのオートフォカス、プログラム露出のフィルム一眼レフで僕と祖父江さんが並んだところをカシャッ カシャッと撮りながら「この前の雑誌に載ってたハービーさんの20代の時のセルフポートレイト、あのハンサムさって凄いですよね!」とほめてくれた。
祖父江さんに言わせると彼女の写真は、写真のルールをはずしたところで、被写体の面白いところを発見しシャッターを切り、また、「決め」のカットではない隙のある写真を使っても十分彼女の写真なんだ、ということだ。僕は僕の写真のルールがある。文法と言っても良いかもしれない。被写体を画面の中心に置かない構図の取り方、逆光や斜光を積極的に取り込む光線の使い方、表情の見極め、こうした僕なりの写真上の文法が長年の間に自然に身に付いている。もはやそれからは逃れられない。これはこれで僕の個性なのだが、梅佳代さんはこうした文法という枠をあえて持たず、ただ無邪気なこころで絶妙なタイミングでシャッターを押す。これが彼女の個性なのだ。そこには何事にもとらわれることなく、シャッターを押した衝動だけが写る。
日本語を例にして僕と梅佳代さんを比較してみよう。「この洋服はとても素敵です」 これが文法的に正しい表現だとすると、僕なりの文章として「君が着たらきっと恋しちゃうな!」と表現する。梅佳代さんだったら「もう、カワイイ!!」を品良く発音する表現になるだろうか。
この夜、僕は、彼女の人間としての魅力に圧倒されながら、彼女の写真が無類に純粋なんだと思え、なんとも素敵な気分になったのである。