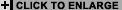第63話 『笑顔という始まり』
9月に始まった、キヤノンの個展が11月2日、無事終了した。2月の谷中のカフェ、4月の四谷ルーニー、8月〜9月の広尾インスタイルと神戸TANTO TEMPO、9月から11月の品川キヤノン、そして現在10月から12月まで仙台KALOSで開催中と、個展がかなりあった。その間に「1970年 二十歳の憧憬」とエッセイ集「僕の虹 君の星」の出版があった。
3月から8月までの間の暗室作業では、個展用と書籍の入稿原稿用に、印画紙を1000枚近く消費した。
個展の中で最も規模が大きかったのはキヤノンで、昨年の川崎市市民ミュージアムと同様、一生に何度も出来る規模ではなかった。
「発表の場を持たぬ写真家は、農地を持たぬ農夫のようなものだ」とかつて誰かに言われた。
その意味では、規模の大小に関わらず、これだけの発表の場を与えて頂けた僕は、それぞれの機会を企画して下さったギャラリーやメーカーの方々に、深く感謝しなければいけない。
東京都内や近郊は、出来るだけ会場に顔を出し、お客様と会話を積極的にするのを僕のモットーとしている。
不意に僕に話しかけられ、一瞬は驚かれて、引いてしまう方も、徐々に慣れて、記念写真を撮ったりしている。お客さん同士を紹介し合い、メルアドを交換し合い、笑顔で会場を後にする。こんなお客さんの嬉しそうな表情を見るのが大好きだ。寂しそうに一人で会場に来て、寂しそうに一人で帰って行くお客さんを見ると、いてもたってもいられなくなる。それは、僕が人一倍、幼少年期に孤独を体験してきたからだ。
会場が空いていれば、全員に話かけられるが、混んでいると手が回らない。
先日も、キヤノンでのことだが、僕が何人かとお話をしている間に一人の制服の女子高生が来て、一人で帰って行った後姿を見かけた。
追い掛けて行って、肩をたたいて、「今日は来て頂いてありがとう!」と言ってあげれば良かったのに、、。僕の胸が少し痛んだ。
一人の作家と話を、または笑顔を交わした、挨拶をした、、、それだけで人間にはポジティブな感情が生まれ、きっと将来に渡って、良いことにつながるのだ。
最終日だったか、会場にいた全員の方々を集めて僕が話をしていた時、僕の知り合い Tさんが会場に来てくれた。
全員、お互いに初対面の関係であったが、場がなんとも暖かかったので、Tさんは勘違いし、「ここにいる皆さんはハービーさんの知り合いなの?」と言われた。
「いや、皆今、ここで知り合った人たちだよ。」と説明すると、なんとも信じ難い表情を浮かべた。
11月4日、森山良子さんがパーソナリティーをなさっているFM番組の収録を行った。これまでのゲストはどんな方かお尋ねすると、竹内まりや、矢野顕子 由紀さおり、さだまさし、らのベテランレンミュージシャンたちである。
森山良子さんというと、以前のエッセイ集「日曜日の陽だまり」に良子さんとの出会いを書いたページがある。僕が高校生か大学生になったばかりの頃の話だ。
良子さんの透明な歌が好きだった僕は、アルバムを買い、周知のヒット曲以外の曲と出会った。「二つの手の思い出」、「愛する人に歌わせないで」。特にこの2曲の歌の、良子さんの透明な声に支えられた哀しく、切なく、美しい曲調に、僕の美意識は大いに刺激されたのである。
レコードを聞く時は決まって傾いた優しい西日が、近くの木々を通過して、白いカーテンをまだらに薄赤く染めていた時間帯だった。何度、これらの曲を聞きながら僕は涙を流したことだろう。
公園で出会ったSAYOが、僕に人間として最も美しい表情を見せてくれて、僕のビジュアルの美意識を育ててくれたのと同様、良子さんの歌は耳からの美意識を育ててくれたのである。
ご本人にお会い出来たのは、僕が十代の後半に差しかかったある日、渋谷道玄坂にある、YAMAHAの店頭ライブでのことだった。カメラを持参した僕は、ミニコンサートが始まる前、良子さんか近くにいたスタッフに「写真を撮っても宜しいでしょか?」と
蚊の鳴くような小さな声で尋ねた。その結果、「どうぞ!!」と良子さんの笑顔が返って来た。
この、笑顔に、病弱で孤独ばかりを味わってきた僕は、どれだけ勇気づけられたことだろうか。
もし、彼ら、ご本人が、怖い顔をして、「写真はやめて!」と言ったとしたら、はたして僕は写真を続けていただろうか、とふと思うことがある。
それ程に、人の笑顔とか、優しい心は人を救うのである。
2004年だったか、初対面の森山直太朗の撮影の時、僕は彼に、今の話をしたのである。「僕のおふくろ、良いことしたんですね!親子2代でお世話になります、、。」
その瞬間から、直太朗の僕のカメラに向けた瞳が一変したのである。レンズの奥の奥を覗きこむ様な、彼の心を見せてくれたのである。
その数年後、彼のアルバム、「風待ち交差点」のライナーノーツのための写真を撮った。各ページには直太朗の自然は笑顔が沢山使われた。
僕は収録前に、このライナーノーツを良子さんに見せた。
「直太朗はこうしたものを私に見せてくれないから、、。」と言いながら、彼女はページをめくった。
「あらー!これは、普段の直太朗そのままの顔ね!!よそ行きの顔じゃないのよ」、と良子さんは嬉しそうだった。
さて、良子さんとの収録は、順調に進んだ。
「今日ね、ハービーさんが、『二つの手の思い出』をリクエストしてくれていたから、ギターを持ってきてハービーさんの前で歌おうと思っていたの。何年か振りでこの歌を家で練習していたら、この時代の自分の、今では失くしてしまった何か大切なものを感じて、涙が流れてしょうがなかったの、、。今日は咽を痛めちゃって歌えないんだけど、コンサートをしても、この時代の歌はずっと歌っていなかったのね。
私たちミュージシャンって、常に今に時代に追いつくというか、常に新しい何かを吸収して歌に込めようとする意識が強いでしょ。だから、古い歌を歌う機会がなかったのね、、。」
「僕としては、この時代の歌は、良子さんの一つの原点として大切にして頂きたいですね。」
「ハービーさんの、この二十歳の憧憬に出てくる写真には、そういった、今は失ってしまったものが写っていてね。エッセイ集も同じで、この当時の心持ちが思い出されて、読みながら何度も涙が出てきて、、。」
「この写真展のためにテーマ曲を入日 茜さんと書き下ろしたんですけど、最初、彼女に、失ってしまった、人を信じる心を という原案を僕は伝えたんですけど、彼女はそれを、失ったんじゃない、忘れているだけ、人を信じる心を、と
書き換えたんですね、ただ、忘れているだけ、、と。それでこの歌に希望がみなぎり、救われたんです!」
「そうね!忘れているだけ、、。そう思えばいいのよね!」
良子さんとのお話は尽きることなく、続いていった。
ふと、正気に戻った。
思えば、僕が高校生が大学生だった頃、手の届かないところにいた良子さんに道玄坂のYAMAHAでお会いした。それから40年が過ぎた今、彼女が僕の目の前にいて、こうしてラジオという舞台でお話をさせて頂いていることが、にわかに信じられなかった。あの日、「写真撮ってもいいのよ!」と言って、僕に見せてくれた良子さんの笑顔に救われたことが僕の写真人生の中の一つの始まりであった。
今日の番組出演は、何の取り得も才能も無かった僕が、その後、僕なりに一生懸命生きてきた結果の神様からのプレゼントであった。
生き続けること。こつこつとでもいいから、一歩一歩、誠実に努力を積み重ねること。その先に必ず希望があるんだから、、。
そんなことを改めて思った、写真展が一段落した、秋口の様に暖かく、美しく晴れ上がった、とある日の午後だった。