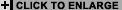【写真展開催のお知らせ】
『My London Punk Life』
2012年10月12日(金)〜12月15日(土) 火〜土曜日開催 13〜18時
場所:Blitz Gallery
〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-20-29
TEL:03-3714-0552
http://www.blitz-gallery.com
第83話 『ロンドンの音』
1983年、撮影の目的で、元セックス・ピストルズのボーカル、ジョン.ライドンの自宅へお邪魔したことがあった。
20畳程の広いリビングルームは、さぞかし散らかり放題だろうと想像していたのだが、僕の想像を見事に裏切り、適度に整理整頓してある住まいだった。
その年、彼はパブリック・イメージ・リミテッドというグループを結成した。通称PILである。
この時代はパンクロックが徐々に下火になり、代わってニューウエーブが頭角を現してきた過渡期だった。破れたジーンズにドクター・マーティンという編み上げの革靴、黒い革ジャンに鋲を打ったり、スプレーでメッセージを書きなぐったり、鶏のトサカの様なモヒカン頭が周囲を威圧した。そうしたアグレッシブな印象のパンクとは対極に、ニューウエーブ、特にニューロマンティックスと呼ばれる一派は、可能な限りの創意工夫を凝らしたメイクと自前の衣装を身につけてクラブやコンサートに現れた。
その代表的なグループの一つが、ボーイ・ジョージが率いるカルチャークラブだった。
70年代後半のパンクの時代、ジョニー・ロットンが音楽やカルチャーの中での時代の寵児だったのに対し、美しい女性のようなメイクを施したボーイ・ジョージの妖艶な風貌が、たちまちにして80年代初期のイギリス、そして世界の若者の話題となった。こうした80年代の前後の数年は、パンクとニューウエーブが入り交じった不思議な時代だった。
ニューロマンティックスが集まるクラブには、デビュー前のボーイ.ジョージがいて、黒いレザージャケットを着て髪の毛を逆立てしていた。初めて彼と「BLITZ」というクラブで出会った時から、彼は常に僕にフレンドリーで、会う度に前回とは違うメイクと衣装に僕は圧倒され,その都度何枚かのシャッターを切った。
それから半年後、僕が居候していたグッジストリートの36番地の最上階に、ジョージは家主のジーンとコネがあったのか引っ越してきて、僕たちはお風呂や台所を共有して生活する様になった。古い家並みにあるこのフロアーはかなり痛んでいて、傾きそして、みすぼらしかった。いくら寒くて古めかしい家でもお金の無い僕にはありがたいすみかだった。
ある日、ジョージがいない夜、こっそりと彼のベッドで寝ていた。彼のベッドの方が僕のベッドより寝心地が良かったからである。夜中の2時くらいだったろうか、いきなりベッドの脇の電話がなった。ジョージからだった。「ハービーかい?実は頼みがあるんだ。僕のボーイフレンドのカークを知っているだろう!彼の電話番号が僕の机の上のメモに書いてある筈だから、カークにすぐに電話をして僕に電話をかけてくれと頼んで欲しいんだ。今僕はバーミンガムにいて、ロンドンまで電話するお金がないんだよ。ここの電話番号を言うからメモしてくれないか?」
僕の対応が早いのでジョージは僕がジョージの部屋にいたことを察したらしい。彼の声が、何かを探る様に低くなった。
「Are you sleeping in my bed??」
僕は一瞬ためらったが本当のことを言った。
「Yes, I am. Do you mind? Because your bed is better than mine.」
わずかな沈黙の後、彼は明るさを取り戻し「No, I don't mind, you can use my bed!」と言ってくれた。
この沈黙は、ジョージのある青春の一時期の心の中に、僕という人間を友人として存在させるスペースを空けてくれた瞬間でもあった。僕はほっと安心した。
男も女もゲイも、僕の様なストレートも、偏見を持ったり分け隔てたりすることなく、自然に混ざり合って暮らしていた。
彼の衣装ケースやメイク道具が散乱した机の上を撮影しておけば良かったと今になって後悔している。
まさか1年後、このジョージが世界を席巻することになるとは、数名いたこのフロアーの同居人の誰もが想像していなかった。
同じ頃、ニューロマンティクスの集まるクラブの一つ、「グレート・ウォール」にジョニー・ロットンが仲間を数名連れて姿を現したのを僕は目撃したことがある。彼とは面識が無かったがカメラを持っていた僕は近寄って聞いてみた。
「May I take some of your photographs?」
彼と数人の仲間たちは僕を睨みつけ言い放った。
「You may not!!」
その強いきっぱりとした言い方に、近くにいたニューロマンティックスの若者は一瞬凍った様な表情を浮かべた。
「嫌な奴!」これが生のジョニー・ロットンの印象だった。
それから一年後の1983年、PILが結成された時のランカスターゲイトのホテルで行われた記者会見には世界中の音楽ジャーナリストが集まり、ある記者がジョン・ライドンに質問した。
「ボーイ・ジョージのことをどう思いますか?」
この質問にそこにいた一堂が答えを待ち構えていた。”He's got the voice"
この一言がジョン・ライドンから発せられた。「いい声してんじゃないの、、。」 ジョン・ライドンは、次の時代のヒーロー、ボーイ・ジョージの資質をある程度認めていたことがうかがえた。
同年ジョン・ライドンの部屋に僕が訪れた時、彼はマクドナルドのハンバーガーをぱくついていた。彼の後ろの壁には、PILとKARATEと書かれたポスター、そして赤、黄、緑の3色の布製のジャマイカの国旗をあしらった壁かけが留めてあった。彼は日本の武道、そしてジャマイカに関心があるのだろうか。こうした時代のスターの素顔に触れた時、日本に関連のあるものに興味がある事がうかがえると、日本人としてはとても嬉しく思うものだ。おどけた表情を何度も僕のカメラに向け、一年前「You may not!!」と言った時のアグレッシブな態度は すっかり影を潜め、彼はとても同じ人物とは思えない程フラットな性格になっていた。「日本式に肩をマッサージしてあげるよ!」というと「くすぐったいから嫌だ!」と言って彼は部屋中を逃げ回った。きっと僕が彼をグレート・ウォールで見かけた時の態度は、時代の移り変わりに心をすリ減らしていたのではなかったかと想像した。その時のことを話してみたが、「Can't remember.」とだけ小さく答えた。
次に僕の目を捉えたのは大型のスピーカーだった。落ち着いた美しい木目を持ったその姿は、一見して英国製の代表的スピーカー「タンノイ」だとわかった。
クラシックに向く柔らかな音を再生するのを特徴としていたスピーカーだ。パンクロックのヒーローとクラシック音楽に適したスピーカーとの組み合わせがとても意外だった。何故ならきっとパンクロッカーは、赤や青色のスプレーで乱暴にPILと書きなぐられた安手のラジカセを使っていると想像していたからである。
その想像を裏切り、彼の部屋には高価なオーディオが揃っていたのである。彼の世間でのイメージと実際のギャップに僕は一種の興奮を覚えていた。
「タンノイ」が好きなんですか?と尋ねてみた。彼は良く聞いてくれたと言わんばかりに、”Tannoy is the best!" と得意げで嬉しそうな表情を見せた。彼は英国を愛する精神の持ち主なのだろう。
それから数年が経った。僕は10年以上のロンドンでの生活を切り上げ、日本に戻ってきて東京の実家で暮らしていた。
ある日のことだった。不意にオーディオが欲しくなった。東京の日常が何か物足りなく、自宅であのジョン・ライドンと同じ音を再現してみたいという衝動が僕に起こった。
この時、ある後悔が僕を支配した。ジョン・ライドンの家を訪問した時、僕はPILのポスターを背景に彼のポートレイトを撮るのに夢中で、部屋全体のカットやオーディオを一切撮影しなかったことだった。
「スピーカーの前に立って下さい」または、「音を聴かせて下さい」とお願いしていたら、彼は快く僕のリクエストに応えてくれただろう。大型スピーカーだったことは印象に残っているが、残念ながら正確にはどの品番の「タンノイ」だったのか、どこのアンプを使っていたのか、どんな音を再生していたのかまでは不明だ。
当時、日本では比較的小型の家庭用の「スターリング」というタンノイが売り出されていたが、僕はさらに小型の「グリニッチ」という新発売の「タンノイ」を買った。スピーカーは大きい方がより良いだろうが、この「グリニッジ」という名前が凄く好きだったからだ。
「グリニッジ」はテムズ川の河口にある街で、港にはカティーサークという純白の大型の帆船が保存されている。かつて英国はこの帆船でお茶の葉を中国から輸送していた。ある時、この船が故障しインド洋で停泊中、船倉のお茶の葉が蒸れて、偶然に紅茶になった。そして英国人はその蒸れた紅茶を好んで飲む様になったという話しを聞いたことがある。
さらにこの街はGMT(グリニッジ・ミーン・タイム)、つまり世界標準時の起点になっている、いわば世界の中心地なのである。
この街の名前を冠したタンノイがとても可愛く思われたのだ。
ジョンのスピーカーはこの「グリニッジ」の4倍の大きさはあっただろう。だからここ東京ではジョンの部屋に鳴っているだろう豊かさや低音の迫力は出ないだろうが、このスピーカーから流れ出るレコードやCDの音にはかすかなイギリスの香りが漂っていた。
ロンドンのあの街角、あの公園の緑、あの空の色、そして友人の一人一人の表情や声、小さな部屋の窓からの景色、、。たった数年前までの幾層ものロンドンでの記憶が、このスピーカーからこぼれ落ちる音と溶け合い、それは映画のラストシーンを見ているかの様に心に響いた。
将来僕は再び外国に夢をはせて、長い海外生活で送るのだろうか、それとも日本にこのまま定住するのだろうか?
僕の日本のパスポートには英国にずっと暮らして良いスタンプが押されていた。どちらに住もうが自由にすれば良いボヘミアンな人生だった。
1987年、僕が37歳の頃だった。