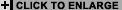第87話 『ロックフォトグラファーの光と影』
僕が人生で初めて世界に名を轟かすミュージシャンと会話を交わしたのは、サンタナのドラマーとして活躍したマイケル・シュリーブだった。
彼はサンタナの2代目の若きドラマーとして、映画ウッド・ストックに登場し人気を呼んだ。
1970年前後、僕が大学生だった時代にサンタナは日本でも大人気で「ブラック・マジック・ウーマン」や「サンバ・パティ」といった名曲がいつも頭の中で繰り返し鳴っていた。
その彼と1976年のロンドンで交流を持つことが出来た。サンタナを脱退した彼は、オートマティック・マンというバンドを結成しロンドンで公演をした。
その彼がサンフランシスコに帰る際、ヒースロー空港までタクシーに同乗した彼と僕が交わした会話があった。僕の最大の疑問を彼にぶつけてみたのだ。
「ねえ、なんでサンタナを辞めたの?あれだけの人気グループでプレーしていたら、名誉もお金も保証されていたのに?」
「人生はね、名誉やお金だけじゃないんだ!自分の力でどれだけのことが出来るのかを試すのも人生なんだ。君はカメラを持って、僕はドラムスティックを持って人生を試しているんだ。だから君も僕も同じ人生を歩んでいるんだよ!」
ヒースローに向かう途中に見える美しい牧草地帯を眺める少年の様に澄んだ瞳を今でも憶えている。その彼の言葉が、人生の右も左も分からなかった僕の心に後々もずっとひっかかることとなった。
それから4年が経った。
ロンドンのコベントガーデンにある小さなレストランでのことだった。
食事と話しに夢中だった我々であったが、店内の照明が落ちたなと気付いた次の瞬間、カウンターの裏からウェイトレスがロウソクを何本か灯した小振りのバースデーケーキを両手に抱え「Happy Birthday To You!!」と歌いながら現れた。
僕たちのテーブル以外の数人のお客さんも笑顔でこの歌に参加した。
一瞬の一体感が人々の間に広がる。レストランでたまに見かける光景である。幸せそうで、ちょっと照れくさく、今日誕生日を迎える本人だったら、きっと慌てるに違いない。
僕は暗闇に光るロウソクの光芒を横目の捉え、ワイングラスの手を伸ばした。誰の誕生日なのだろう、、?
だがケーキは思わぬ方向に進んで来た。なんと我々のテーブルに近付き、僕の前の置かれたのである。僕の目の前の友人の拍手が起き、他のお客さんのこの拍手に加わった。
「エッ? ワッ恥ずかし!俺に? こんなこと初めて!!」
僕はテーブルに座っていた友人と周りのお客さんに小さく会釈をした。
あれは1980年の一月だったか。つい数日前、僕はロンドンで30歳の誕生日を迎えたばかりだった。
このロンドンには1973年に来てから7年、僕は滞在し続けていて、一度も日本に一時帰国さえしていなかった。その間1月20日の誕生日を祝ってもらうような洒落た環境には全く恵まれず、毎年一人ぽっちの誕生日を迎えるのが普通であった。
そうしたある種の寂しさに慣れていたから、このレストランで友人と食事中にバースデーケーキが僕に運ばれて来るとは思いもよらなかった。ロンドンでも、そして23年間過ごした日本でも体験したことのない出来事だった。
僕の4人掛けのテーブルには 日本人の音楽ジャーナリスト、キム・山門、ヴァージン・レコードのプレスオフィスで働くオーストラリア人のミランダ・ブラウン、そしてオランダ人のロックフォトグラファーのアントン・コービンがいた。
キムは時折日本の音楽雑誌での仕事で一緒に取材をする仕事仲間で、彼女が引っ越しをする時など家具の移動を手伝ったりする間柄だった。
ミランダは当時スターを沢山擁していたヴァージン・レコードの海外向け広報係の窓口で働く長身な美人で、僕の様な日本向けの雑誌や日本のレコード会社の取材や撮影の依頼は、このミランダを通して交渉するのだった。そしてアントンはロックフォトグラファーとしてスター的な存在で、数々の大物アーティストのポートレイトを撮影していた。
彼独特のシチュエーションを生かしたモノクロ写真は毎回目を見張るものがあった。
初めて僕が彼の名を憶えたのは、ロンドンで流通している、通称NME、「エネミー」と呼ばれていたNew Musical Express誌の表紙を飾った、ザ・フーのギタリストであるピート・タウンゼントのポートレイトだった。
真っ黒なロンドンタクシーの後部座席に乗ったピート・タウンゼントが窓の中からアントンのカメラに目線を送っていた。
思いもよらぬ状況を考えたものだと、彼のセンスに対し大いに驚嘆を受けたのだった。その後もロンドンのミュージックシーンでの新星や大物アーティストの独特のポートレイトも何度も目にしていた。
カメラマンがジャーナリストという範囲で扱われると、撮影現場は決まってアーティストの事務所か、レコード会社の一室に限られる。単にインタビューに添える顔写真を撮るだけという理由だ。
しかし、顔写真以上の写真を要求される時は、写真家はフォト・ジャーナリストというより独特の視点を持ったフォト・アーティストという認識を相手に与えなくてはいけない。
ここに一つのハードルがあって、写真家がアーティストという世界を持つこと、それを相手が認めることはそう簡単にいかないのだ。売り込み中の新人アーティストの取材、撮影ならまだ可能性はあるが、世界に名を轟かせる大物アーティストを一写真家の世界に引きずり込むというのは至難の技だ。
その点アントンはほとんどの撮影に際し、彼だけのシチュエーションをあつらえることを許されていた数少ない写真家だった。
このコベントガーデンのレストランで僕はその時の悩みを聞いてもらった記憶がある。
「僕はさー、良く日本からの仕事をするんだけど、ギャラが安い上に材料費が出ないんだよね。
フィルムと現像費に出費が大きいからほとんどお金が残らなくて、、。
先月、日本の音楽誌の撮影でジャパンのデビット・シルビアンとパリまで行ったんだけど、いいシチュエーションだったんで、編集者にオリジナルのスライドは将来僕の作品として残しておきたいから、使用後返却希望ということに書いたら、それなら航空機賃と宿泊代は折半したいって返事でさあ、すると利益が残んないわけ、、。
あとね、デュランデュランの写真を日本に送ったら、しばらくして電話があってギャラはいくらですかって聞くから、少し安い価格を言ったんだけど、その一ヶ月後に見本誌が送られて来てさ、見たら巻頭に5ページ、それと折り込みの大きなポスターにも使っているんだ。
こんな沢山使うんだったら何倍もの額を請求しても良かったんだよ、だけど、どれだけの扱いで僕の写真を使ったっていうことをギャラの交渉に時に言ってくれないんだよね。」
ビジネスと撮影とをはっきり区別出来ない僕は、経済的にも精神的にもかなり疲弊していた。そんな自分が情けなくみじめであった。
この言葉に対しアントンはこう言った。
「僕はね、仕事の数が少なくなっても自分の仕事の報酬はすごく高くするんだよ。納得して、良い仕事をする様にしなけりゃいけないよ。」
この言葉を聞いて改めて彼を頼もしく,痛快に思ったものだ。
アーティストにとって自分の作品のクオリティーを保つために、こうした主張はとても大切なことだ。
だが、こうした交渉が出来る人と出来ない人がいるのは事実だ。僕は出来ずに、そしてアントンはそれをやっていた。
僕の場合、アントンの様なシチュエーションが与えられるようになったのは随分後のことで、大抵の場合は多くのカメラマンに混じっての、記者会見の後か先に設定されるフォトコールと呼ばれる合同撮影タイムでの撮影だった。
フォトコールでの撮影は他のカメラマンと似たり寄ったりのカットしか撮れないと思うのであるが、工夫次第ではそうでもないことも経験した。
1983年元セックスピストルズのジョニー・ロットンがPILを結成し、自らの名前をジョニー・ライドンと改めた。その記者会見が彼と契約しているヴァージン・レコードからほど近くのホテルで行われた。
その日インタビューが始まる前の20分間がフォトコールとして設定され、世界中からの音楽カメラマンが彼を囲んだ。
人数としては30名程だっただろうか。
場所は室内で暗く、僕も他のカメラマンもストロボを付けての撮影だった。
だがある時、いきなりテレビの照明が彼に当たった。BBCか民放か、イギリスのテレビ局の撮影が始まったのだ。
彼の顔にその照明による陰影が浮かんだ。その陰影を見た僕は、即座にストロボのスイッチをOFFにした。
ストロボを使えばブレの心配はなく、絞りも稼げるからピントも確実だが、そのかわり,自分のカメラからの一方向の光しか得られないので、被写体に当たる光は平坦になって面白みがない。
一種の賭けであるが、僕は手ぶれやピンぼけになる危険性をあえて踏まえ、ストロボではなくテレビの照明を利用する撮影に切り替えた。そして僕はジョニーの真横に移動して彼の横顔を捉えた。
結果的には実にパーソナルな視点で、ひょっとしたら彼の家で一対一で撮るよりも珍しいカットを撮るのに成功した。工夫次第では何十人とカメラマンが群がるフォトコールでもこうした写真が撮れることを体験したのである。
数日後、この時のプリントをキムに見せた。
彼女は僕の他にもう一人イギリス人のカメラマンに撮影を依頼していたが、イギリス人のカメラマンは終始ストロボ撮影だったため新聞のインタビュー写真的なものだった。
光の起伏に富んだ僕のプリントを見た瞬間、「同じ記者会見で撮った写真なのに、撮るカメラマンによって出来上がるものが死ぬ程違うわね!」と感想を述べた。
アントンは素晴らしい写真を撮り続け、被写体はデビット・ボーイ、トム・ウエイツ、マイルス・デイビスと増々広がっていった。
1990年代に入って僕は日本に住んでいて、渋谷のパルコの書店でアントンの写真集を見つけて買った。
デビット・ボーイが表紙になったハードカバーの立派な装丁のこの写真集はFamouzと名付けられ、その中には、かつてNMEを飾ったロンドンタクシーに乗ったピート・タウンゼントの写真も入っていて、またジョニー・ライドンも、デビット・シルビアンも、その他僕が撮った多くのミュージシャンがアントンの世界観によって撮られていた。
さて、2013年6月、映画「伝説のロックフォトグラファー、アントン・コービンの光と影」というドキュメント映画が公開された。上映館である渋谷のアップリンクで、映画上映後僕のトークショーが行われた。
とても興味深い、写真家には大変示唆に富んだ内容の映画だった。
ロンドン、アイルランド、アムステルダムでの空気感みなぎる映像は美しく、映画に携わったカメラマンの意気込みと制作者のこだわりが十分感じられた。
映画の中でのアントンは僕が知っている頃とは大きく違い、僕より5歳年下の現在55歳になった風格が備わり、顔に生えた髭がとても良く似合っていた。
そして彼は決して大きく笑うことはなく、終始どこか寂しげであった。そして彼がインタビューの中で話すことがらがとても興味深かった。
アントンは牧師の息子として生まれ、そのことで周囲の子供たちから随分と「くそ野郎」と罵倒されていた。
貧しい家庭で寂しい毎日を過ごす中で、身の回りにあるものごとの本質や形をいつも彼なりに観察していた。
そして違う人生を夢想していた。写真を撮り始めてからは満たされない心を写真で埋めている自分がいて、次第に写真に愛情を持つようになった。
父親はプロテスタントの牧師だったため、偶像を持ってはならない思想であったが、その反発からアントンの写真には、ミュージシャンを偶像として讃える画面構成が多く見られることとなった。
ミュージシャンとは、音楽だけを頼りに生きる激しい生き方だ。自分の写真家として、写真だけを頼りに生きてきた。そこに同じ種の人生を生きる者同士の絆が生まれる。
産みの苦しみというか、ミュージシャンが音楽を創作するためにもの凄いエネルギーを使っていて、自分もまた写真に全ての人生を捧げてきた。
そして映画に登場するミュージシャンの言葉が最高の賛辞だ。
ルー・リードは「F◯◯king beautiful! この素晴らしい写真の数だけ新しい曲を書かなくては。アントンの写真には、曲とそれを書いた俺たちの本質が写っているんだ。」
そしてU2のボノは「アントンもU2も作品を通して光を求めているのさ。一瞬のはかない光を、そしてアントンの作品にはアントン自身が投影されていて、被写体である俺たちは媒介なんだ。アントンの撮る写真の中の自分になりたいと思ってる。」
これ以上ない、なんと素晴らしい賛辞であろうか。
そしてアントンのお姉さんの証言がある。
「アントンはずっと仕事ばかりをしているわ。映画の撮影をしていたと思ったら同時進行で別の仕事に出かけて行くし。いつも仕事に追いまくられている。休養が彼には必要なの、いつか倒れてしまわないかと心配で、、」
彼の中の何がこうも彼を仕事に駆り立てるのか?
栄光の中にいるアントンは正直に心境を語り続ける。
「自分は困難が好きだ。不安定で幸せを感じない方が安心する。完璧な作品というのは息をしていないものなのさ、でも自分の作品はまだまだ完璧じゃないからどこかで息づいているんだ。
もっと自分と向き合ってみるよ。これからの人生、もう20年前と同じことをしたくないんだ。いままでは僕が先方に出向いていって写真を撮っていて、そこには新しい出会いの楽しさもあったけれど、今度はこのスタジオに彼らに来てもらえたらと、、。
牧師だった父は人生の中で、お金ではなく、もっと違う価値や結果を求めていたんだ。自分は人間として遅れていると思う。写真を撮ることでは人間との深いつながりは生まれないのかも知れない、、。」
人間にとって何が幸せなのかは人それぞれだし、そしてどの程度の幸せが必要なのかも人それぞれだ。
アントンも僕も、幼児期、少年期にはどこか共通した過去があって、そこから察すると僕も彼も手放しに幸せを手に入れたら写真が撮れなくなるだろう。写真を撮る必要がなくなると言った方が的確だ。
名声と多くのミュージシャンが写った作品を作り、恐らくお金を築いた彼は、この世界では最も成功した一人に違いはないが、少なくともこの3点だけではアントンは幸せにならないのである。
彼の父が求めていた「お金ではなく、もっと違う価値や結果」とは一体なんだろうか。
一つ彼と僕の最大の違いは、彼の写真集「Famouz」が物語る様にアントンは常にその時代に有名なミュージシャンを追いかけている。唯一有名でもなく、人物ではない写真が映画の中で見られたのは,旅先のホテルの窓から撮られた幾葉かの写真だ。その写真にも十分に彼の確かな写真眼が見受けられた。
それに対し僕は、ロンドン時代も日本に帰って来てからも、恐らく有名人に費やした何十倍のフィルムを市井の人々に向けて撮影していた。有名人も市井の人々も同じ社会で生きる人々として等価に眺めていた様なところがある。そこが彼と僕との一番の違いだと思う。
そして、彼の言う「写真を撮ることでは人間との深いつながりは生まれないのかもしれない、、。」という言葉を僕自身に問いかけてみた。すると、その後の人生に生かせる様な素敵な思い出がいくつもあった。
例えば、ミュージシャンがレコード会社の一室での撮影後に僕に尋ねた。
「ハービー、今日は良い写真が撮れたかい?」
「うーん、前回もこの部屋だったから、この前と似たようなカットしか撮れなかったかも。。」
正直に話すと彼らは真剣に僕の言葉を受け止め考え込み、「そうか、、。じゃあね、今度の日曜日は何も仕事が入っていないから、僕の自宅に来て撮影をしないか?」そうした彼らの寛大な好意で僕は何人もの高名なミュージシャンのご自宅に伺ったことがある。
また、ウルトラボックスのオリジナルメンバーだった、ジョン・フォックスとはある夜、
「クリスマスっていうのはさ、一人で住んでいる外国人にとっては寂しさを噛み締める日でね。毎年どこにも行くところがないのさ、交通はほとんどストップしているし!」という僕の言葉に大粒の涙を流し、来年は一緒に過ごそう、と言ってくれた。
そのすぐ後、彼のシングルレコードのリリースがあり、僕がジャケ写を撮るリクエストが来た。一緒にアイデアを出し合い、彼の家で彼のスーツを撮ることになった。
2ヶ月後、出来上がったジャケットには、僕のクレジットが共演ミュージシャンと同じ大きさと扱いで載っていた。
また、U2については、1983年僕がダブリンで彼らを初めて撮った時の話しがある。彼らの創作の拠点である小高い丘の上にそびえる貴族の館を訪ねた時だった。
到着するや、撮影の用意をする僕に向かってボノが言った。「君のことを知りたいな。日本はどんな国で、何故ロンドンに住んでいるのか、そして写真家としてどういった写真を撮って来たのか、、」
出来るだけ撮影は短時間で済ませてしまいたいと思っているだろうと想像していた僕にはこうした彼の態度が意外であった。しかし、「日本には古来から以心伝心という考えがあって、でも西洋でははっきりとものを言わないと認められないところがあって、」と話し始める僕を取り囲み、まっすぐな視線を向けながら熱心に耳を傾けている様子を見るにつけ、彼らの本気度が伝わって来た。
30分程話しただろうか。いつも「人の心を撮りたいと思っている」というところでボノが言った。
「Yes、君のことが少しは分かったよ、さあ撮影を始めよう!僕たちは君のリクエストになんでも応えるから何でも言って欲しいんだ。今日は君の日なんだから、、。」
つまり、こうした会話の結果、ボノの面接試験に合格したのである。
そうしたミュージシャンとの出会いの極めつけが地下鉄で偶然乗り合わせたザ・クラッシュのジョー・ストラマーの態度と一言だ。
不意に投げかけられた僕の撮影リクエストに応じてくれたばかりか「撮りたいものは全て撮るんだ、それがパンクだろ!」との名言を言い残したのである。
たわいのないことだと言われるかも知れないが、その一つ一つの出来事がいまも僕の心の中で宝物のように光っている。
きっとアントンにはこうしたストーリーが僕の何倍もある筈だ。彼はそれをもっと誇り思っても良いのではないだろうか。
人生の目的や答えは人それぞれ違うのだろうけど、ミュージシャンが人生を賭けて紡ぎ出した音楽が、人々を救い勇気を与えてきたように、写真家が人生を賭けて撮った写真は、世界のどこかで人々にある種の刺激といくばくかの希望を与えていると信じて良いのではないかと思うのである。