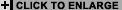第90話 『東京シャッターガール』
映画に役者として出演する機会が今になって来ようとは全く思っても見なかったことだった。今年2013年の6月だった。知り合いの写真家小林幹幸さんから電話があった。
「ハービーさん、お仕事の話しなんですけど、、。失礼だったら本当に申し訳なくて、断って頂いて良いんですけど、、。僕、今、東京シャッターガールという映画を初監督作品ということで撮っているんですけど、ハービーさんに出演して頂けないかと、、役どころは高校の写真部の顧問の先生なんですけど、、。」
そんな電話から始まったこの出演であった。
原作者の桐木さんと監督の小林さんと話し合いで、現役の写真家が写真部顧問役をやったらリアリティーがでるんじゃないかというアイデアが出たということだった。会話の途中、僕はすぐに面白いと思い
「いいですよ、是非お願いしますよ!」と返事を返した。
「えっ!本当にいいんですか??」と小林さんは終始恐縮している態度だった。
実は僕には、へっぽこ役者だった時期があった。僕が24歳の時だった。
僕がロンドンに住み初めて数ヶ月が経ち、お金もビザの残り期間も短くなってきたある日、友人のケンがどこかの日本食レストランの壁に貼ってあった役者のオーディションのチラシを見つけ、大声で僕に報告した。当時アメリカやヨーロッパで絶大な人気を誇っていた、パーカッショニスト、ツトム・ヤマシタさんの率いる「レッドブッダ」という劇団のオーディションだった。
ケンと彼の後輩のタツはすっかりオーディションを受けるつもりになっていた。彼らは僕にもオーディションを受ける様にと進めた。実は役者になる夢を中学の時にふと抱いた経験があった。だがとても消極的だった僕は、その夢をすぐに捨ててしまった。
中学のクラスは違うが同学年に児童劇団に所属してテレビのドラマに出ている女子がいた。「少年探偵団」という子供向けのテレビドラマだった。一度だけ「どやったら劇団に入れるの?」と彼女のクラスに行って質問したことがあった。まじかで見る彼女はテレビで見るよりはるかに色白できれいな顔をしていた。
「審査員の前でね、ちょっとした寸劇をするの!例えばトンボ採りとかね。」
彼女は椅子に座ったままだったので机越しの対面であったが、初対面の僕に感じ良く接してくれた。彼女への好感度は上がったが、人前で一人づつ意見を発表するとか、教科書を読むとか、楽器を演奏するとかが何よりも嫌だった僕には、複数の大人の審査員の前で寸劇をするなどもっての他だった。だからそれを想像しただけで、劇団に入ることはあきらめた。そして彼女とも二度と会話を交わすことはなかった。
中学の時からおよそ10年間が過ぎて24歳になって、しかもロンドンの住んでいた僕は、どこか以前とは違う人間になっていた。そんな僕の生活の中で、ビザを延長するのが最も重大な課題だった。
写真家になりたいという僕の夢をあたかも後押ししてくれているような文化のあるこの国にもっと長く住んでみたかった。この国は日本とは明らかに違っていた。この国の文化の中で、日本では成し得なかったことに挑戦し、ただがむしゃらに生きてみたかった。そうした中から自分の人生の目的やきっかけがつかめる気がしていた。
このままオーディションを受け、もし合格すれば役者になれるという過去の夢が実現するし、劇団員でいる間は多少の収入とビザの延長が期待出来るのだ。それから二週間後、ケンとタツと僕の三人は無事オーディションに合格し、晴れて劇団員として採用されたのだった。
数ヶ月のリハーサルを積んだ後、冬のロンドンの舞台を2ヶ月、そして春になるとスペイン、イタリア、オーストリア、ドイツを廻る海外ツアーに参加した。数えると丁度100回の舞台出演をこなした。
特に印象に残るのが,ミック・ジャガーが観劇に来ていることが楽屋に伝えられたロンドンでのある夜の公演、そして一万五千人を集めたローマの野外劇場での舞台だった。体を使って何かを表現する表舞台を経験した僕はそれ以前とは全く違う人間になれたように思えた。
10年の滞在の後、初帰国して間もなくの1985年、渋谷の近く、国道246号線に面した一角に「子供の城」が開館した。そのこけら落とし公演としてツトム・ヤマシタさんが「天地の夢」という舞台を作、演出した。僕は再び三日間の舞台に立つことになった。
あれから28年が過ぎた。三たび表舞台に立つ機会が訪れたのだった。東京シャッターガールは高校の写真部に属する男女の生徒が、写真に関わることで様々な葛藤にぶつかり、悩み、また人々に触れ合うことで成長していく物語だ。原作は漫画になって2冊が刊行されている。その漫画の映画化である。
早速小林さんから台本が届いた。写真部の部員にアメリカの作家の写真集を説明しているシーン。そして荒木経惟さんの写真集「センメンタルな旅、冬の旅」を手に、写真家になることの覚悟を切々と訴えるシーンが書かれていた。ざっと内容を把握して撮影に臨んだ。
6月のある日、JR中野駅のすぐ近くにある廃校で撮影が行われた。原作者の桐木さんを紹介された。細身で物腰の柔らかな青年だった。この時彼の話しから知ったのだが、原作の漫画に登場する東京の芝にあり、窓から東京タワーが見えるという設定の高校は、正則高校をモデルにしたという。偶然、実際に僕が卒業し写真部の部長をしていたのがこの正則高校だった。何か僕のためにある様な映画に思えて来た。
写真部の生徒役の可憐な女の子たちや、繊細な男子部員を演じる彼らに紹介された。実に爽やかで明るい彼らだった。「実は、僕は本当は写真家なんだよ。」と言うと彼らは一様に驚きの表情を見せた。
撮影現場は虚像である筈だが、ここが実際の教室だったこともあって、大きな窓から注ぎ込む元気一杯の夏の光の下、彼らの白く輝く制服や赤いリボンにはリアリティーがあって、無邪気な笑い声を聞いていると紛れもない現実の高校の中にいる錯覚にとらわれた。
特に演技指導はなかった。撮影の合間、高校生役の彼らにカメラを向けた。その撮影は写真部顧問の先生としてごく自然の行為として受け入れられ、彼らに近付くのに有効な手段だった。背景に主演の夢路歩役である田中美麗さんがいて、湊部長役の田口夏帆さんの顔が手鏡越しに写っているカットを撮影するのに要した数分は、映画の撮影現場にいるという認識を忘れる素敵な時間だった。そうした共有した時間を経て撮影は進んだ。
写真って何だろう、とそれぞれの価値観を戦わせながら悩む高校生たちが僕を囲み、カメラが回ると台詞が自然と出て来た。荒木さんの写真集を手にしながら生徒を見回す。
「最近、先生が気がついたことがあるんだ。それはね、この写真は、実は荒木さんが撮ったんじゃないかも知れないって。亡くなった陽子さんが荒木さんに撮ってって天国から頼んだんじゃないかって、、まるで遺言のように、、。そうした深い悲しみを乗り越えて、荒木さんは世界に名を轟かすカメラマンになったんだね、、。」
どこかで、荒木さんが僕に乗り移ったかの様な気がした瞬間だった。
「写真は鏡!どうしたって自分が写ってしまうものなんだ!」
それぞれの台詞には小林監督の写真への想いが正直に綴られていた。現役の写真家にこうした台詞を言わせたかった制作者側のこだわりが果たせた瞬間でもあった。
映画の編集が終了してところで、小林監督は荒木経惟さんの所に行き、映画の中に荒木さんの写真集を登場させ、また、「陽子さんが、、」という台詞を語っていることをご挨拶がてら報告したそうだ。
「ハービーが演ってるんだったらしょうがないな、、!!」と荒木さんは笑っていた。
映画「東京シャッターガール」は10月に池袋の映画館で封切られ、11月から12月にかけて東京都写真美術館で上映された。11月30日、この日の上映が終わった後、桐木さん、小林監督そして僕の三人が舞台挨拶をし、その後トークショーが開催された。
小林監督は、「僕の写真観がハービーさんと違っていたら、あの台詞を言わせるのが凄く失礼じゃないかって、ずっと心配していたんですよ!」と幾度となく言った。
それに対し僕の答えは「いえ、違っていることは特にないですよ。同じ写真家として、ほぼ同じ価値観を持っていますから。ただアメリカの写真家の写真集を見せる場面では、僕だったらフランスの写真家の写真集を見せるかなっていう違いですかね。でもこれは小林さんの作品ですから、それを曲げてはいけませんし、僕は一役者に徹しなければいけないと思っています。」
次に小林さんが興味深い話しをした。
「アメリカでの体験なんですけど、笑顔というのはコマーシャル写真の中に溢れていて、その逆にアートとしての作品には人の苦悩が写されている訳で、、。」
その言葉のお陰で僕は自分の写真とか人生の本質が見えてきた。
「僕が幼児期に煩った病気が少年期まで続き、そうすると教室の生徒や先生の意地悪な視線にさらされる訳ですね。誰も僕を仲間に入れてくれないとか。ずっと孤独と絶望の中で生きてきましてね。すると僕に向けられる笑顔が世界のどこかにあるんじゃないかってずっと探しているんですよね。美味しいご飯より、人からの笑顔が欲しかったですね。だから僕は自分の作品の中でも笑顔を求めちゃうんです。それが僕の特徴でもあり、また限界なのかとも思います。でもね、自分なりに精一杯生きていると神様が時としてプレゼントをくれるんですよ。ギタリストの布袋さんが、最初のソロアルバムの時に僕に詩を書いてくれと頼んでくれたり、その歌詞がカラオケに入ってます。そしてこの映画出演もそうです。桐木さんと小林さんからの大きなプレゼントです。そうした時に今までやってきたことを正直に出せばいいんです。今年僕は63歳ですけれど、ますます人生が楽しいですよね!どんどんいろんなことが出来てる訳ですから、、。」
7時に始まったトークショーは9時近くまで和やかに続いた。
写真美術館を出ると、めっきり冷たくなった冬の夜風が、熱気でほてった頬に気持ち良かった。
ここ恵比寿ガーデンプレイスには色鮮やかなクリスマスのイルミネーションが点灯され、人々の心を照らしていた。「人生を俄然やる気にさせてくれたね!!」クリスマスにはまだしばらくの間があるけれど、ここを歩く誰よりも早く「東京シャッターガール」という素敵なプレゼントを僕は頂いたのだと実感するのであった。