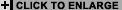第78話 『PUNK IS NOT DEAD』
8月のある日、僕は東北新幹線に揺られ一路盛岡に向かっていた。外は晴れていて真夏の太陽が、早回しされた映像のように流れ去る風景を浮き上がらせていた。
車内は空いていて隣の席も空席だったので、そこには大きなビリンガム製のカメラバックが置かれていた。その中には、ライカのM3、M6、MPが一台づつ、レンズは28ミリ、35ミリ、50ミリ、そして予備に85ミリを付けた一眼レフ一台、そして、コダックのT-MAX400のフィルムが50本入っていた。撮影に出かける時、移動中でも出来る限り撮影機材は網棚に乗せないで、少しでも自分に近くに置いておきたいというのが写真家の心情だろう。
咄嗟の時、すぐにカメラが手が届くところにあるということは安心につながる。そして僕は時折り、ずっしりと重たいカメラバッグを膝の上に置いてバッグを両手で抱き込みしばらく目を閉じる。目的地に着いたら、思い描く写真が撮れますようにという自分の気持ちをカメラに込める儀式や祈りのようなものだ。傍目には赤ちゃんを胸に抱きしめる母親の姿に見えるかも知れない。マリナーズのイチロー選手が、ブルペンから出て、正確な歩数でバッターボックスに向かい、一度足に屈伸をして、ボックスに入り、バットを大きく回す。そんなルーティーンを通して精神を集中させるのと同じなのだろう。
靴はイギリス時代に買ったドクター・マーティンという編み上げの革製のブーツだ。これは当時、階級社会に反旗を掲げ、社会からの向かい風に対抗し、必死に生きていたパンクロッカーの必需品だ。皆この靴を履いてロンドンの街やコンサートに出かけた。黒と赤の二色があり、高いのと低いのとの二種類があった。赤をロンドンの彼らはRedとは言わず、Ox Blood,牛の血の色と呼んでいた。僕はこのOx Blood色の低い方をロンドンで履いていて、帰国時に日本に持って帰って来た。
僕が気を引き締める時に決まって履く靴だった。1988年、J-WAVEのラジオ番組を生放送でいきなり始めた時にも、僕は大抵スタジオにこの靴を履いて行った。
盛岡の駅で落ち合ったのが、僕の次男のPだった。Pは高校二年生であるが、この夏休みのほぼ一ヶ月をかけて、北海道から沖縄までの日本縦断旅行の最中だった。
青春18切符というのがPの交通手段である。鈍行列車ならどこえでも移動出来るのだ。Pは7〜8時間かかって北海道から盛岡にたどり着いた。
盛岡は東京よりかは少しは気温が低かっただろうか。しかし、まだまだ酷暑は東北でも続いていた。
僕たちは小型のレンタカーを駅前で手配し、早速岩手県の大槌町に向かった。中目黒で雑貨店を経営している方の友人が、大槌町で復興作業のボランティアをしていると聞いたので、その方を訪ねることがまず最初の手がかりだった。これまでに、石巻や女川、東松島と撮影はしてきたが、大槌町は始めて行く町だった。
駅から休み休み車を走らせ、3時間程かかると聞いていた。途中一つ二つの道の駅に寄った。その一つで、地元の写真家による、昭和初期の東北の人々の暮らし振りを撮った写真展がこじんまりとしたスペースで開かれていた。
素朴な、または過酷な自然と戦う暮らしぶりが活写されていて、しばらくその十数点の展示を見つめていた。地方には、こうした我々が知らない、けれど確実に名作を撮り続けてきた写真が多くいるに違いない。東京という中央でその作品を発表することもなく地方に埋もれている逸材を、こうして道の駅で展示することは大切な事だとつくづく思った。
山を越え、車は徐々に海岸線に近付いていった。ボランティアの方とは、大槌町の入り口にあるローソンで待ち合わせた。
4月の初旬の石巻の瓦礫に埋づもれた街の様相から比べると、震災から半年近く経っているので、道路を塞いでいるものはなかったが、道路の左右には津波に無抵抗のまま破壊し尽くされた家屋や地形がそのまま残されていた。
ローソンの駐車場で僕たちは無事、ボランティアの彼と出会う事ができた。このローソンは、近隣には似た様なマーケットがないので、人々には最も便利にされているお店だそうだ。
お昼時には、このローソンに作業している人達のほとんどがお弁当を買いに来る。僕のレンタカーの隣には、大阪県警と書かれたパトカーが止まり、中から、大阪からの応援隊であろう警察官が、このローソンにやはりお弁当を買いに来ていた。
震災直後には、マーケットに7時間列を作って並び、やっとおにぎりを一つ買う事が出来、家族で分け合って食べた、と話してくれた人がいらしたが、物流が回復した今では、品物は行き渡っているようだった。
しかし、車を運転しない高齢者の方々は、遠くの家や避難所からここまで買い物に来る事が出来ない筈で、どうしているのだろうと思いを巡らした。
ボランティアの彼は北海道の出身で、2ヶ月もこの街に住み込んで復興作業に携わっているという。1〜2階は浸水したものの、建物の骨組みや壁が残っている物件の内部に溜まった泥の掻き出しや補修をして、取りあえず住める状態にまで戻す作業を手伝っていた。僕とPは彼が作業しているお家へお邪魔して、丁度お茶の時間だったので、先程のローソンで買ったものと、東京から持って来たものを開けて、また、このお家の方が用意したおにぎりを進められたので一緒に頂いた。
休み時間が終わると、Pは彼なりに指示された通りの掃除を手伝い始めた。
僕は、近所のお寺で破壊された墓地を修復している様子や、隣の元ビジネスホテルの中を見せてもらった。そのホテルのオーナーの息子さんという彼が、「6階の屋上に上って、街の風景を見て欲しい、どうぞ写真を撮っていって下さい」と仰るので付いて行った。
その高いところからの眺めは、いかにこの街が巨大な津波で洗い流されてしまったかを如実に見せていた。歯が抜けた、または壊れた櫛のように無惨にも家の土台だけが見渡す限り続き、所々に建っている全壊を免れた建物が寂しそうにポツリポツリと残されている。でもその家々の壁には、スプレーのペンキで、「撤去可」とか、「取り壊して下さい」、と書かれてあった。
何時間後、僕とPはレンタカーに乗り、海岸線に行ってみることにした。10分も走ると、そこは街外れというか住宅地ではなかったところなのだろう、平地に瓦礫だけが散乱する荒涼とした光景が続いていた。
陸地に打ち上げられ、45度に傾いた中型の漁船が2隻見えた。その漁船の近くに車を止め、僕とPはカメラを持って船に近付いていった。船だけが取り残されていると思ったのだ。
すると2隻の漁船の間には、日陰作るためビニールシートがテント代わりに張られていて、そこで20人程の漁師さんとおぼしき、日焼けをした筋骨たくましい男達達が作業を一休みしているところで、僕たちはづかづかとその人達の中へ不用意に入って行ってしまったのである。彼らはそれぞれ片手に30センチはあるナイフを持っていた。
一瞬の沈黙があった。彼らも突然のカメラを持った我々に好奇の目を向けた。後にはすでに引けなかった。僕は大声で叫ぶしかなかった。僕がまず素になることである。
「東京から写真を撮りに参りました。皆様の復興に賭けるそのお姿、一枚シャッターを切らせて下さい!!」
その結果彼らは、言葉を僕に返すでもなく、小さな、はにかんだような表情を浮かべた。
僕は胸にカメラ3台をかけ、一人一人に近付き、シャッターを切る度に「オッス!!オッス!!」とお礼を言いながら、次々とシャッターを切った。
5分もすると、「さー、始めるかっ!」と言って一人が立ち上がると全員があとに続き、漁船の反対側に移動した。そこには、ロープや網が津波で絡まり合い散乱していた。彼らはナイフで、絡み合ったそれらを材料別に裁断し、廃棄する作業をしているところだった。
先程から僕が気になっている20代の若者がこの中にいた。彼はイギリスのパンクロックのヒロー、ジョニー・ロットンの顔が描かれた白いTシャツを来ていたのである。タイミングを計って,彼に近付いた。
「お若いですけど、ボランティアさんですか?」「いえ、漁師の息子です。」
「パンクがお好きなんですか?」「ええ!」
「30年も前ですが、僕はロンドンに住んでいて、そのジョニー・ロットンの写真を実際に撮っていたことがあるんです!」
その言葉を聞くと彼は、とても嬉しそうな顔をしてカメラに向かってポーズをとってくれた。「是非、ロンドンの写真集と、今撮らせて頂いた写真をお送りしたいのでご連絡下さい」と彼に名刺を渡した。
1980年代の始め、パンクが陰りを見せ、ニューウエーブが台頭してきた頃、ロンドンの街の壁にらく書きされた言葉が頭をかすめた。パンクロッカーたちの合い言葉だった「PUNK IS NOT DEAD」。まさか、30年前のロンドンと2011年の大槌町で復興に命を賭ける若者と僕とをパンクが結びつけてくれるとは想像もしなかった。
Pはそうした彼らと僕の様子を遠巻きに見守っていた。
彼ら一人一人の写真が撮れたと実感し、再び、「ありがとうございました!」と深々と頭を下げ、僕たちは車に戻った。彼らは笑顔で遠ざかる僕たちを見送ってくれた。
翌朝、盛岡から仙台に僕たちは向かった。乗車券と座席指定券は前日に買ってあった。駅ビルでラーメンを食べていて、ふと時計を見るとあと10分で新幹線が出てしまう時間だった。僕とPは大急ぎで地下道を通り改札口へ向かった。その直前、ポケットをまさぐると切符をいれておいた財布が無くなっていた。途中で落としてしまったのだ。
Pは自分のチケットを持っていたので問題はなかったが、僕は、ラーメン屋さんに戻って探さなくてはいけない。近くにいた制服を着たJRの方にPのチケットの乗車変更を頼んだ。「僕の指定券は、買い直せばいい。」
僕は地下道を走って戻った。すると場内アナウンスが流れた。「ヤマグチさま、落とし物がインフォメーションデスクに届いています。」財布が、現金もカードもチケットも全て無事に届けられていた。
インフォメーションの女性に訪ねた。「お礼を是非、拾って下さった方にお礼をしたいのですが、お名前を教えて頂けますか?」「地下街の◯Xキッチンというお店の若い女性です」という答えが返ってきた。
その店に行ってみた。店長さんがいた。「あー 彼女は今ランチタイムで1時に店に戻ってきます」「是非、お礼をしたいので、連絡を頂きたいと仰って下さい」と店長さんに僕の名刺を渡した。
改札口に戻り、先程の制服の方にチケットを見せ、「指定券を買ってきます」と言った。すると、その彼が、「私が一緒に窓口まで行きましょう」と付いて来てくれた。そして、窓口の中の女性に「これ、乗変扱いでお願いします」と言ってくれたのである。
仙台駅で僕とPは別れた。Pは自分の旅を続けるため、仙台から高速バスに乗って新潟に向かい、僕は新幹線で東京に向かった。
数日後、Pは広島にいる頃だった。2通のメールが届いていた。一通は大槌町のパンクの漁師さんから、住所、そして「写真を楽しみにしています」という内容だった。もう一通は、財布を拾って下さった彼女からだった。
「店長から名刺を渡されました。その名刺を見た瞬間、手が震えました。実は私は、ハービーさまの若い役者を撮った写真集を何冊も持っております。盛岡から東京まで、なかなかお芝居を観に行けないので、ハービーさまの写真集を見てファンになったり、応援したりしています。お財布が無事届いて良かったです。お礼なんか決して要らないんですが、実は、祖母と二人で市内で暮らしているんですが、その祖母が、ハービーさまの撮られたテレビドラマの「優しい時間」の写真集が好きで毎日見ているんです。
その祖母はこの震災で、大槌町というところに住んでいた友人とか身内を無くし、とても落ち込んでいて、今年は桜が咲く季節になっても、外に出ようともしませんでした。もし、もし良かったら図々しいお願いなのですが、祖母に、風景写真を一枚送っていただけないでしょうか。決してご無理はなさらないで下さい。ハービーさまに直接メールしていることが今でも信じられません」
数日後、漁師さんには、ロンドンの写真集とジョニー・ロットン、そして彼自身と、その時に撮らせて頂いた漁師さん達のプリントを送り、お財布の彼女には、桜とブランコが写った「丘の上のブランコ」と題したプリントを送った。
すぐに写真が届いたというメールが来たが、財布の彼女は文章の端々から、僕にメールしている事が信じられない、という高揚感が伝わって来て微笑ましかった。
そして漁師さんの彼からはクールながらも、人間としての根幹を感じさせるものだった。
「写真届きました。僕たちのかけがえのないものを形にしていただいてありがとうございました。写真集は、僕は写真の専門知識はないのですが、当時のロンドンの熱気を感じました。ロットンの写真は友達に自慢したいと思います」
彼の「かけがえの無いものを形にして、、」という感謝の気持ちに僕はどれだけ救われただろう。僕の写真が少しでも彼の役に立てたのである。
東京駅から、カメラバッグにできるだけの機材とフィルムを入れこみ東北に向かう度、僕の心は揺れ動いていた。写真家として、人間として、隣に困っている人達がこんなに沢山いるのだから、何をすべきなのだろうとずっと考えていた。写真家であるから、その得意分野を少しでも生かせてお役に立てたら、と願うところまでは、心に誓うのであるが、実際に被災した人々の前へ出で、カメラを至近距離で人々の向けるという行為は勇気が要ることだった。
「あんたら、テレビ局だか、雑誌社か知らないけど、俺たちあんたらの見せものじゃないんだよ、好きでこんな哀れな格好してんじゃないんだから。」
もし、そう言われたら、僕はどう撮影行為を受け入れてもらうように説得出来るだろうか。テレビ局や新聞社に属さない、フリー写真家としての信念が問われ続けられるのである。
だが幸い、そうした言葉を仰る方には一人としてお会いしなかった。皆が、生きるか死ぬかという時に、人間としての尊厳を僕のカメラに見せてくれていた。そうした彼らの態度に毎回励まされる思いだった。
この誇り高い精神性を、世界に届けようとの確信が僕の中で毎回膨らんでいった。
漁師の彼とは,その後も何通かのメールのやりとりがあった。
「東京から何かお送りしましょうか。大分寒くなってきました。」
「いつも,そこまで手厚く気を遣って下さってありがとうございます。僕たちは笑顔を絶やさず頑張っていますよ。山口さんこそ、冬に向かって体をお大事になさって下さい。」決して弱音を吐かない彼であった。
秋も深まったある日、ホカロンやレトルトの食品を送った。
そして、この3月、印刷が出来たばかりの写真集「HOPE 311 陽、また昇る」を送付した。彼はこの写真集に4カット出て来るいわば主役だ。
翌々日、彼のおばあちゃんからお電話を頂いた。
「いつもいつも、申し訳ありません、孫のUにいろいろと送って頂いて、、。」心から恐縮しているという気持ちが伝わってきた。
「どうですか、漁業は再開出来そうでしょうか?」
「いえ、それはまだ無理で、Uは今貨物船に乗って、コックをやっています。今度は5月に帰って来るそうです」
東北のために一人一人が出来る事をしなければ、そう改めて思うのである。