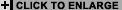【写真展開催のお知らせ】
『ハービー・山口写真展』
Chapter 1
「1970年、二十歳の憧憬」
前期/2012年8月25日(土)〜9月30日(日)
Chapter 2
「僕の虹、君の星」
後記/2012年10月6日(土)〜11月11日(日)
場所:ミュゼふくおか カメラ館
〒939-0117 富山県高岡市福岡町福岡新599番地
TEL:0766-64-0550
http://www.camerakan.com/special/year2012/herbie_Ymaguchi/index.html
第81話 『僕の彼女は女子アナ』
久しぶりの北海道、2012年8月1日は曇り時々雨で、東京では考えられない肌寒さを感じる一日だった。数日滞在の予定でライカを2台バッグに入れて、どこまでもなだらかに続くニセコの自然にレンズを向けた。北海道の広い風景を眺め、空気を胸一杯吸うと、東京でのストレスが洗い流されるような気持ち良さがある。
北海道の主要都市に行くと、かつて1980年代の後半から90年代後半まで、様々なアーティストのツアーに同行して、北海道の風景と共に彼らのグループショットやポートレイトを撮影した思い出がよみがえってくる。
例えば、小樽の近く、銭函の海岸線の高台にある、一面10数メートルのガラス張りのカフェがあった。眼前には日本海が見え、床には椅子もテーブルもなくクッションの 上に座るなんとも洒落たカフェだ。そこで初期のドリカムを撮った。お店の入り口には確か、「ラストオーダーは崖の下を通る最終列車の汽笛」というような文章が書かれてあった気がする。
また、雪の積もる山中で、ストリート・スライダーを凍えなら撮影した。撮影の後札幌に戻り、コンサート終了後の楽屋で、ボーカルのハリーが僕の肩に手とあごを乗せ、札幌の夜景を眺めながら「いつまでも仲間だぜ!」と小さく僕につぶやいた。EPOのコンサートでは、彼女が風邪をこじらせていて雪の中ホテルから会場に移動するのにも辛そうだった。しかし、ライブは大成功に終わり、その結果数時間前までぐったりとしていた彼女の風邪の症状は完全に消え去り、見違える程元気になって深夜までスタッフと飲み明かした。何かを表現し、お客さんと一体になることがどれだけの肉体的、 精神的新陳代謝を促すのか驚くばかりだった。
福山雅治さんとは東京から札幌に着くや、地元のプロモーターの車で、本人と僕を含めた数人で車を飛ばし、余市の近くのお寺に行った。この数ヶ月前、海岸線のトンネルが崩壊し、運悪くトンネル内に差しかかったバスに乗っていた何名かが犠牲者となった。その中に男子高校生がいて、その彼がバスの中で聴いていたのだろう、車内から発見されたウオークマンには福山雅治さんの楽曲が入っていたことが報じられた。このことを知った福山さんは、飛行場から真っ先にお寺に直行し、高校生のお墓を探してお線香を上げたのだった。
ジュディー・アンド・マリー、大江千里、山崎まさよし、吉川晃司、佐野元春、19、、。ここ北海道は、あの時代を象徴するミュージシャンとの沢山の思い出がある。
1990年代中期だったろうか。そうしたミュージシャンが札幌に来ると決まって訪れるラジオ局があった。たしか札幌の時計台の近くにあったAM局だった。僕もスタジオに同行させてもらったが、この局に高瀬さんという音楽に造詣が深いディレクターがいらして、東京から来るミュージシャンは決まってこの高瀬さんに会いに行くのだった。東京とは違う北海道から、確実にその時代のミュージシャンを見守っている良き理解者だったのだろう。高瀬さんの興味の対象は音楽ばかりではなかった。
例えば、僕がロンドンから帰りたての1984年前後、僕と面識がないのにも関わらず、札幌のパルコで開催したロンドンをテーマとした僕の写真展にも、女性のアナウンサーを連れて来て下さって、僕へのインタビューはもちろん、会場のお客さんの声を拾いながら、かなりの長い間を取材に費やして下さった。後日、カセットテープで同録を送って下さり、それを聞いた僕は番組のクオリティーの高さに驚いた記憶がある。イギリスの街やロックグループに関する質問はもとより、僕のイギリスでの生活の様子、そして、写真展に来て下さったお客さんの声を拾い、それは30分程の特番に近い扱いになっていて、僕という人間とロンドンの日常をテーマとした声と音の世界が描かれていた。僕のコーナーのエンディングに、高瀬さんのチョイスなのだろう、スタイル・カウンシルのインスト曲、「BLUE CAFE」が流れた。ちょっとメランコリックで、それでいて優しく美しいメロディーラインに、正に僕の一人ぽっちの寂しさと、当時のイギリスのアーティストと交わる興奮とが象徴されているようだった。この曲を僕の出演コーナーの締めに使うセンスは、高瀬さんの洋楽の知識と技術を遺憾なく覗かせていた。
そうした流れの中で、ツアー中のあるミュージシャンが札幌の近くの病院に入院している友人を見舞いに行った。僕もカメラを持って同行したのだが、僕がトイレに行っている束の間、彼らと病院内ではぐれてしまった。どの病室だろうと入院病棟をうろうろしていた。
そして、僕が廊下の角を曲がろうとするとふいに現れた、全速力で走ってきたパジャマ姿の小学生位の女の子と正面衝突をしてしまった。僕の胸にぶらさがっていたカメラが彼女のおでこを直撃したのである。
「痛いっ!」と言って彼女はその場にうずくまってしまった。
「ごめん!」僕は彼女の顔を覗き込んだ。幸い、おでこが少し赤くなっているだけで、切れたり血が出ていたりはしていなかった。
「もう平気」と言って彼女は立ち上がった。
「ごめんね、僕の不注意で、、。」
「いえ、あたしが廊下を走っていたのが悪かったの、あたしの方こそごめんなさい」
彼女は僕のカメラを見ると興味深そうに「おじさんってカメラマンなの?」と聞いた」
「そう、今夜の○×さんのコンサートを撮りに東京から来たんだ。その前にちょっと用があって、この病院に来たんだけど」
「ふーん、○×さんか! あたしも退院したらいつかコンサートに行ってみたいな」
彼女の声は底抜けに明るく、大きな目がくるくると動いた。
「ねえ、おじさん、あたしの病室に来て!いいもの見せてあげる。」
彼女は病院生活が退屈でしょうがないのだろう。興味あるもには何でも飛びつきたいのに違いない。
僕は一瞬躊躇したが、彼女の後について行った。近くの病室に入るとベッドが3つ置いてあって、彼女のベッドは一番窓側だった。窓越しに見える外界は、太陽の傾いた 日差しに照らされ、白いビルが少しだけ赤く染まりつつあった。
彼女のベッドの枕元には、この歳の女の子らしく、アイドルが写った雑誌が何冊か積まれてあった。彼女はその中の一冊を取りページをパラパラとめくって、あるアイドルの男の子が微笑む写真を僕に見せた。
「あたし、この子が大好きなの、ね!素敵でしょっ、おじさん、この子を撮ったことある?」とくりくりと目を輝かせた。
残念ながら、その男の子は人気のアイドルだったが、僕は撮ったことがなかった。
「いや、撮ったことないな、もっとミュージシャン系の人たちは撮るんだけどね。 」
彼女は少しがっかりした様子だったが、すぐに表情を取り戻した。そして僕は積まれている雑誌の中に、月刊カドカワの背表紙を見つけた。
大抵の号に僕の写真が載っていた。僕は手を伸ばし雑誌を取ると、奥田民生さんのインタビューページを開き彼女に見せた。
「これ、僕の写真さ!」そこには奥田民生さんとミスチルの桜井和寿さんとが対談している写真や、僕のリクエストで壁に掛けてあった時計をおろし、二人で持って頂いてカメラに向かって明るく笑っている写真だった。
「えっ!そうなんだ、すごい!!」彼女は初めて嬉しそうな表情を浮かべた。それは彼女が初めて僕をカメラマンだと認めてくれた瞬間でもあった。
「僕、そろそろ帰らなくちゃ」そう言って彼女にさよならを言った。
「また、札幌に来たらここに寄ってね、でもあたし、退院しているかも知れないけど。もしそうだったら、あたしとは縁がなかったっということで、あたしのこと引きずらないでね!!」
そのおませな彼女の言葉と笑顔に半ばあきれながら病室を出た。僕は運良く一階上で、ミュージシャンと合流出来、撮影はしなかったが、彼の素顔が見られて同行させてもらった甲斐があった。
それから一ヶ月後、僕はまた違うミュージシャンの札幌厚生年金会館での撮影のため札幌を訪れた。
コンサートが始まるしばしの間、いつもは会館から歩いて数分のカメラやさんに行って中古のライカを見て過ごすのだが、あの小学生が気になってタクシーに乗って病院に行ってみた。もう退院している筈だった。
だが同じ病室に彼女はいた。ボヤーッと、じっとうつむいていた。彼女は僕の顔を発見するや急に元気な表情を見せた。
「来てくれたのね!!」体を動かして遊びたい盛りの彼女にとって病院のベッドは退屈以外の何ものでもないだろう。
相変わらず何冊かの雑誌が積まれてあった。その上にイヤホーンが巻かれた小さなラジオがぽつんと置いてあった。
「ラジオ聞くの好きなの?」
「うん、夜中とかテレビつけると周りに迷惑でしょ。夜中に目が覚めて、独りぽっちで眠れない時は大抵ラジオを聴いてるの。」
「そうなんだ。まてよ、僕がたまにラジオ番組にゲストで出る時があるんだけど、そのいくつかはfm north waveとかにネットと言うんだけど、東京の番組が北海道にも流れるんじゃないかな」
「エッそうなの、おじさんの、いや、おじさんじゃない、ハービーさんの声が札幌でも聞けるの!?、だとしたらあたし最高に嬉しい、だってあたしラジオで気分を盛り上げているんだから。」
「昔ね、ずーっとラジオ番組を続けている福山雅治さんにね、どうしてラジオにあんなにこだわるのって、聞いたことがあるんだ。そしたらね、中学か高校の時、長崎の自宅で、ふと真夜中に目が覚めちゃう時があって、こんな夜中に起きているのは日本中で僕だけだろうって、寂しく思うときがあって、そんな時ラジオをつけたら、DJの元気な声が聞こえてきて、すごく救われたんだってさ。それで自分がラジオ番組を持てるようになったら、寂しい人を勇気づけてあげたいって思うようになったんだって、、。
実は福山さんは高校時代にお父さんを亡くしているんだ。夜中にふと目が覚めた時の寂しさは想像以上のものだったろう、その彼を助けていたのが深夜のラジオ だったんだね。でも彼の凄いところは、自分の弱みを絶対に人に言わないことだね。 彼の歌詞の中に彼の世界観があるんだよ。」
「ふーん、そうのだったのね、正に今、あたしがラジオや音楽に助けられているんだものね。あたしもいつかラジオ番組やってみたい。そして入院している人たちを笑わせたり元気にしてあげたい!」
「僕もラジオ番組を毎週持っていたことがあるんだよ、影響力って凄くあってさ、この間、僕の幼稚園に行っている子供が風邪を引いたんで、毛利さんっていう小児科の先生の所に連れて行ったの。そしたら受付で先生と話ししていたら、近くにいた大学生くらいの女の子に、ハービー・山口さんでしょって、声をかけられたんだ。毎週僕の番組を聴いているから、その声と話し方ですぐにわかりましたって、、。凄いよね! 誰がどこで聞いているかわからないし、ラジオにしろ、音楽や写真や文章や映画や、そうした全ての表現物で、自分の世界感、価値観を出せて、それが人に伝わって、人も自分も元気になったら、それは凄いことですよ!」そんな僕の話を彼女は目を輝かせて聞いていた。
「10年くらい前の話だから君が生まれたか生まれてなかったかという時のことなんだけど、パルコで写真展を開いた時、札幌のラジオ局が取材に来てくれたんだ。その番組を後でテープで聞いたら、素晴らしい仕上がりで感心したんだ。写真展を舞台にして、僕から上手くアナウンサーがインタビューしてくれて、それを素材にして、ディレクターのセンスで曲を交えながら完璧な30分の作品になっていたんだ。情報番組や、曲ととりとめのない日常会話で終わる番組とは全く異質の、聞き流すのはもったいないラジオで聞くアートなんだね。こうした番組に仕立て上げるクリエイティブな感性とラジオの美学をもったディレクターに出会えるというのは、アナウンサーにとっても、僕のような出演者にとっても幸運なことなんだよ。自分で気がつかない良いものを見つけてそれをディレクターのセンスで包んでくれて素晴らしい作品に仕上げてくれるんだから、、。そうした、しっかりと自分の世界を持った優秀なディレクターが何人かいるんだよね。
良いものっていうのはラジオでも、音楽でも写真でも映画でも、送り手自身や受け取る側の心を元気にしてくれる力があると思うんだ。」
僕は、話の相手が何も知らない小学生ということを忘れて、一人興奮して喋ってしまった。
しかし、彼女は大きく目を見開いて僕の話を聞いていた。それはまるで一つの部屋の中の生活しか知らない動物が、急に開け放たれた窓から外界を眺めた時の驚きと開放感に衝撃を受けたような表情だった。彼女はまだ見たことのない、果てしなく広がる地平を見つめていたのだろう。
そして思わぬ言葉が飛び出した。
「ねー、あたし、将来女子アナになりたい!そしてラジオ局かテレビ局に勤めて、そしたら番組持てるんでしょ?もしそうなったら!」
「まあ、そうなんだろうけどね。でも女子アナになるのは大変だよ。綺麗で、頭が良くて、英語が喋れる人も沢山いて。選ばれた人たちだね、女子アナっていうのは、、。なりたけりゃ、一生懸命勉強しなくっちゃ!でもこうした入院の経験なんか があると、弱い人の気持ちが分かって、将来大切な財産になるかも知れないね。結局ね、人にインタビューするだろ、その時、聞き手として、いかに相手の気持ちを全人格を持って引き出して受け止めて、自分の言葉でリスナーに伝えられるかなんだよ。
そうだ、北大を目指そう。あそこの環境は凄いね、小川が流れていて、芝生があって、ポプラ並木がずっと続いていて、まるで北欧にいるみたいだよ。
ああしたところで4年間青春を過ごせるなんて幸せだよね。そして夏休みはずっと貧乏海外旅行に費やす。いろいろなことを見聞きすることが君を育てるんだ。君は器量もいいし、10年後には立派なレディーになっているだろう、頭の回転も速いから、北大出身の美人女子アナが生まれる可能性大だな!
でなければ、学歴に関係なく世間とか世界を自分の足で歩いて、破天荒な経験を経てフリーで頑張るかだよね!
そうだ、今度、東京から僕の本を送ってあげようか?東京のJ-WAVEっていうラジオ局で僕がレギュラーで喋っていたフィール・ザ・ヒーリ ングっていう番組が、そのままのタイトルで単行本になってるんだ。番組が一冊の本になって残るっていうのは、そんなに頻繁には無いんだから。
最近知ったんだけど、大阪のFM802っていう局の立ち上げの時の企画会議で、僕のかつてのJ-WAVEの番組が取り上げられて、こんな番組を大阪でもやりたいよねっていう一例になってたんだってよ!!」
彼女は一層目を輝かせて、未来の自分を見据えているようだった。
それから半年ぶりに札幌を別のアーティストの撮影で訪れた。
病院に行ってみた。もう彼女はいる筈がないと信じていた。だが意に反し、彼女の名前は、別の病室の入り口の名札に見つけることが出来た。こんなに長く入院しているなんて、あんなに元気そうなのに。
病室に入るとやはり窓際のベッドが彼女の場所だった。季節が前回と違う。初秋の爽やかな高い青空に薄く白く、うろこ雲がゆっくりと流れていた。
彼女は眠っていた。目を閉じて、そして僕が送ってあげた単行本が、お腹のあたりにしっかりと両手で包み込まれるように置かれていた。いや見方によっては、四六版の単行本にしがみついているといった方が正確かも知れない。起こしてはいけないと僕は静かにその場を去ろうとした。廊下に出る寸前、突然彼女の声がかかった。きっぱりとした声だった。
「ハービーさん!行かないで!」
「眠っていたんじゃないの?起こしちゃってごめんよ。」
「ねえ、約束してくれる?あたしが女子アナになったら、一回目のゲストはハービーさんって!」
「もちろんさ、東京から真っ先に飛んでくるよ!」
「ありがとう、、。」
そう言うと彼女は、安心した様にまた目を閉じた。お腹のあたりの毛布が息をする度に上下していた。
また、眠ってしまったようだ。僕は静かにその場を去った。
それからはしばらく札幌に行く機会はなかった。そして北海道のことは日々の忙しさと都会の喧噪の中で忘れかけていた。
季節は春になろうとしていた。一通の白い封筒が届いた。札幌の消印だった。
半分もその手紙を読めなかった。それは札幌の彼女のお母さんからの手紙だった。
「もうすぐ春が来るという季節、まだ気持ちの整理がつかないでいます。娘の早紀は、春を待たずに静かな眠りにつきました。娘はうすうす、退院出来ないことを感じていたようです。
でも、ハービーさんに会えたことで、早紀はいつの日か女性アナウンサーになってラジオ番組を持つ希望を胸に、幸せな夢の中で最期の数ヶ月を過ごすことが出来ました。ハービーさんから送って頂いた本を片時も離さず、何度も読み返してはずっと幸せそうな顔をしていました。
早紀には父親がおりませんもので、ハービーさんは、早紀にとって父親であり、兄であり、ませた女の子でしたので、恋人だったのだろうと想像します。偶然のご縁とはいえ、、。」
僕はラジオのスイッチを入れた。札幌でFM NORTH WAVE といえば82.5。東京ではNHK・FMが入る。その周波数の近くを探してみた。
ザーザーという大雨か砂嵐のような雑音だけが耳に刺さった。その一瞬遠くから声が 聞こえた。
「こんにちは、入社一年目、新人アナウンサーの○×早紀です。今日からこの番組を 私が担当させて頂くことになりました。まだまだ勉強中ですがどうぞ宜しくお願い致します。春めいてきて、街の街路樹はフレッシュな緑でキラキラと光り、そして私の心の中もキラキラです。さて、この後、私にとって記念すべき第一回目のゲストは、 東京から来て下さいました写真家のハービー・山口さん!実は、私の恋人!わー、告白しちゃった!いえ、私がとっても尊敬している写真家です! そのハービー・山口さんをお呼びしています。後でじっくりお話を伺います。」
聞こえる筈もない彼女の声が雑音の隙間をかいくぐって僕に届いた気がした。
あれから十数年が過ぎた。2012年8月、僕はレンタカーを走らせてニセコに向かっていた。
小高い丘の上で車を止めた。彼方に、一見富士山と形が似ている羊蹄山が姿を現していた。
うだるような暑さの東京とは明らかに違う25℃、澄んだ空気と一面の緑、そしてたんぽぽが丘陵全体を覆っていた。
この地域では、周波数が変わって79.5がFM NORTH WAVEだ。カーナビに付いているチューナーをいじり、何度もAIR-Gとの間を彷徨った。
もしかして、あの声が聞こえてくるのではないか、、。そう期待してしまう自分がまだここにいる。
「ようこそ! 夏の北海道へ!!」
「僕が君の分まで喋っているから、そんなに心配しなくたっていいからね、、!」
空には彼女にふさわしい透き通った夏の青空がどこまでも広がっていた。