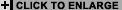|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 > 第53話 『ブライトンからの出発』 
第53話 『 ブライトンからの出発 』写真家にとって、写真展を開催出来るということは、もっとも嬉しいイベントの一つだ。現在目黒で2月6日までヨーガンと僕の2人展を開催している真最中だが、このため生活に張りがあって精神的に充実しているのが正直な気持ちだ。 写真を撮影している時、「よし、良いのが撮れたぞ!」という高鳴りが写真家にとって最も幸せな瞬間だが、その作品をギャラリーに飾って、来廊して下さった方々が評価して下さった時が2番目に幸せな瞬間だろう。 この2人展を開くにあったって何をプリントしようかと先々月、頭を巡らせていた。ヨーガンのプリントは去年の内に日本に届いていたので、その内容を知っていたので、それを参考にすると、同じイギリスで撮られたものが良いだろう。そして出来れば同時代に撮られたものが良いだろう、という考えにまとまった。 ヨーガンは僕より20年近く先輩なので、僕がイギリスに行く何年も前にイギリスに渡っている。祖国ドイツを離れ、南アフリカで何年も過ごし、フランスやイギリスに時として滞在した。送られてきた彼のプリントは1968年にイギリスのグラスゴーという北の街で撮られたものだった。その時代のイギリスを僕は知らないが、写真から見ると、かなり経済的に疲弊している。街には古びた建物が並び、瓦礫が散乱し、その中をみすぼらしい格好をした子供たちが遊んでいる。いまの明るいファッション色に満ちた華やかな街並みとは対照的だ。その中で古い伝統を誇るパブ(酒場)が市民の憩いの場所として栄えていた。ビールやウイスキーを飲みながら話したり踊ったりしている人たちが多く写っている。街は暗く、しかし、人々の心は、塞ぎがちだが憩いの時間だけは明るさが戻り、この時代のつつましやかな時代性を見事に表現している。 1968年といえば僕は18歳で、思い返すと大学浪人をしていた時だった。大田区にある実家から、40分程かけて原宿にある代々木ゼミナールに通っていた。来季の入学試験に向けて一心不乱に勉強していたかというと、実はどこかうわの空で、勉強にはあまり身が入らず、写真のことや、いつか、たどり着けるだろう僕のユートピアのことを夢想していた。 18歳から数えて5年後 1973 年、どうにか拾ってもらった東京経済大学を卒業した。しかし、何社か受験した就職試験に対してもどこかうわの空で、結果、どの企業にも拾われず、ならばいっそ海外に行って、24時間写真漬けの毎日を送ってみよう、と思い立ったのが、大学時代の友人、磯辺君と一緒にイギリスへの半年間の旅だった。半年経って、精一杯撮った写真をどこかの雑誌社に売り込むか、個展を開いてフリーランスの写真家としてのキャリアをスタートさせたい、というのがおぼろげな構想だった。 したがって僕のイギリスで一番古いネガは1973年だ。 場所はロンドンではなく、ヒースロー空港に着くや、ロンドンは素通りし、ヴィクトリア駅から小一時間、ブライトンという海に面した街だった。1973年9月23日だった。車窓から広い緑の畑や木々が見える。そして、遠くに小さな集落や、小さな街並みが見え隠れする。 まるでおとぎの国の中の可愛い街並みが、絵本のページをめくる度に現れてくるかの様だ。 英語学校に入り、午前中は勉強、午後はすべて自由な時間だ。日本から持参したニコンを僕は四六時中手放すことなく、「あっ!綺麗だな、可愛いな、素敵だな」と思ったものを素直にとり続けた。 生まれて初めての親元を離れての一人暮らしの自由快活さと、想像を超えたこの街ブライトンの透明な空気に触れ、僕は今まで体験したことのない、生きる喜びを一瞬一瞬に感じ取っていた。 特に人々の表情が印象的だった。日本にいた時は人々にこれ程の感情を、顔の中に見ることはまれであった。しかし、この街の人々は、その時々の感情を、特に、嬉しい時や人生を楽しんでいる時の精神性を表に表していた。 豊な表情と言ったら良いのだろうか。日本より豊な人生を垣間見る、と言ったら良いのだろうか、人々の日常の中に、日本より何倍もの精神的な余裕を見たのだ。例えば、日本では、何かが流行っていると、その流行りが自分に合っていようがいまいが、いち早くその流行りを手に入れないと、置いていかれてしまうような、焦りとか慌ただしさ、不安を感じたものだ。自分の様な特に秀でた才能の無い者は、多数の中の一個人だと確認することで安心につなげていた。多数から外れることへの心細さに支配されていたのである。少なくとも僕の中では、社会の趨勢が個人より優先しているのだ。 日本だと、かなり有名にならないと個性は尊重されない。一般人が強い個性を持つと、社会に適応しない変人に扱われてしまうのだ。 だが、この街の人は、まず自分が根底にあって、それを一番大切に思いながら、社会へのつながりを持っていく、という生き方だ。いくら流行っていたって、自分に合わなければ、その流行りを無視したって良いじゃないか。流行りに動じない自分の個性が毅然として存在しているのだ。その個性を社会は尊重してくれていた。 僕はまるで鎖をはずされた飼い犬の様な自由さを満喫した。かといって勝手気ままに生きているのか、というとそうではなく、教育によって作られていた、インテリジェンスという名の、社会の中での常識を逸脱しない理性は、個人がちゃんと持っているのだ。 これは生きていてすごく精神的に楽だ。自分主体に清々堂々胸を張って良いのだから。その精神性が大人や子供に関わらず彼らの表情に正直に出ていた。僕の被写体として絶好であった。 毎日通う英語学校の近くにいつも遊んでいる子供たちがいた。次第に顔見知りになり距離が縮まっていった。ある良く晴れた日の午後、傾いた太陽に照らされた一人の 5 、 6 歳の少女にカメラを向けた。僕の顔をすでに知っているので、特にカメラを意識することはなかった。彼女は自然にしていてくれた。シャッターを切り終えると、長かった僕の髪が目を覆った。それを見た少女が僕の方に近づいてきて、手を伸ばし僕の顔にかかった髪を指でとかしてくれた。そこにはただ素直な人間同士の自然な行為が存在していたのである。 ある日、女子高の中に入って行った。校庭では放課後に入った生徒たちが嬌声を上げて遊んでいた。105ミリの付いたニコンを彼女たちに向け、数回のシャッターを切った。彼女たちは僕に「HELLO!」と言っただけで遊びを続けていた。 背後から声がした。「校内に無断で入らないで下さい…」男の先生が立っていた。すると、この先生に対し彼女たちがこう言ったのである。「彼は日本から来て、ただ私たちの写真を撮っているだけじゃない!私たち撮られたって構わないのよ!」 校則は曲げられないので僕はその場での撮影は続けられなかったが、先生は紳士だった。そして、彼女たちの言葉が何より嬉しかった。特にこうした少女たちがとても美しかった。長く伸びた手足はとても健康的だったし、長いブロンドは降り注ぐ陽によって、舞台の照明を当てられたかのようにきらきらと輝いていた。まるで天使が舞い降りてきたようではないか。僕の部屋から歩いて数分で海岸に出られた。日本と違って砂浜ではなく、砂利の海岸線だった。遠くに船に影がゆっくり動いていた。そして、海と反対方向に車を走らせると丘陵地帯が続いていた。その頂上にデビルス・ダイクという丘の頂上があった。下方にどこまでも続く畑が緑色をたたえ真平らに拡がっていた。畑の間を整備された道が風景にアクセントを加え、自動車が一台、二台ゆっくりと進んでいた。畑の中には良く見ると羊の群れが所々にあって、雲間から陽が差すと羊がキラッ、キラッと光った。 このたおやかな空気は、この平和な心持は…今まで味わったことのない、この世の楽園のごとくであった。 36年振りでこのブライトンで撮ったネガをプリントした。ベタ焼きは無く、ネガを透かせて直感で選んだ。25枚程プリントした。このうちの3枚は、写真集に収められているが、他は初めてプリントしたものだ。36年前の空気や僕の新鮮な心が浮かび上がって来た様だった。 それにしても、今と作風が全く変わらないのだ。当時23歳の僕は、今と比べて、撮影の要領も悪く、写真の教育を受けていないのだから上手い写真を撮る方法も全く解してなかったであろうに、まるで今年撮ったかの様なのだ。東京の都心の様に、街の風景が再開発によって一日一日変っていくわけではないので、今年撮ったと言っても、「ああ、そうなんですか」と言われそうだ。 グラスゴーと違って、比較的裕福なイギリスの地方都市だからなのか、時代や人々には今より余裕がずっとあって、そのせいか写真が撮り易かったのも大きな一因で、僕の西洋への新鮮な感動と見事にコラボレートしている。 作風が変らないという事実は、23歳にして僕の写真はすでに完成していたのか、それとも以後37年間に渡り、これといった進歩が僕にないのか、どこか不思議な感覚を抱くのである。 ただ、一言いえるのは、「あっ ! 綺麗だな、可愛いな、素敵だな」という、 [ 憧れ」を感じた対象に、素直な心をもって、そっと近づき、静かにシャッターを切っていただけなのである。そこに、写真界の新たな動向とか流行りの作風を取り入れるとか、または「人と違う写真を撮りたい」という意識は全くなかった。つまり、奇をてらうとか、どういう写真なら「斬新な表現」として写真家や評論家、編集者の目に止まるかなどの意識は一切なかったのである。例えて言うなら、僕の写真心というものが、シャーレーの中に入っていて、外界からの雑菌が全く侵入しない無菌状態で37年間、いや写真を始めた中学2年生の頃から数えれば46年間、純粋培養されてきたんじゃないかと想像するのだ。 それにしても、日本を離れ第二の人生を写真と共に、被写体の豊富なこの街で、心洗われつつ始められたことを僕は幸運だったとつくづく思うのである。
ヨーガンと僕の二人展「Two in One in England]が2月6日まで開かれています。是非ご高覧下さい。 |