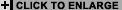|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 > 第15話 『デジタルとフィルム』 
第15話 『 デジタルとフィルム 』 いよいよライカM8の登場だ。フィルムカメラの王者ライカがM型デジタルカメラを作ったのだ。 タレントの写真集もデジタル全盛だ。ポラを使う代わりにモニターの画面をタレント本人に見せつつ撮影する。すると納得した顔をしてその後の撮影はスムーズだ。かつてのフィルム時代、現像の上がりを見るまで結果が分からない苛立ちや、テストロールを見て増減感しなければならない不便さとはもう無縁となったのだ。撮影が終わるとアシスタントと、「デジタルで良かったね。フィルム交換の必要も、番記をつける必要もないんだから…なんと楽なんだろう。」と話が弾む。 ところがである。ことモノクロームで自分の作品を撮ろうとすると僕は100%ライカのM3、M6、MPにT-MAX100やプレストをつめて外に出る。M型ライカにフィルムを詰め、そして自分の暗室でバライタにプリントするのが断然好きなのだ。例えばライカM3、50年も前のこのカメラが絶対的な精密感を持って手の中にあるという感触は、ライカ以外のカメラではまず得られない独特のものだ。そしてフィルムに潜像として残る達成感、それは豊かな心に通じる充実感に他ならない。そして僕は3台所有しているフォコマートの引き伸ばし機を駆使し、美しいバライタ紙にプリントする。完成品を見ると写真をやっていて良かった、僕は生きている、と実感するのだ。便利なデジタルを仕事で充分使いながら、作品ではなぜライカとフィルムなのだろう。これは一概に説明出来ない抽象的な感覚だ。生理的に僕には一番気持ち良い組み合わせといったら良いのだろうか。 さてこのM8、僕が作品を撮る時にもデジタルに移行する掛け橋となり得るだろうか。掛け橋になって欲しいという気持ちと、もうちょっと待ってくれという気持ちが複雑に絡み合っている。 |