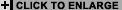第31話 『 目の教養 』
数年前、あるギャラリーで三人展という構成の写真展を開いた。僕の他、二名の方々は日本の写真界を代表する写真家で、僕にとっては誉れ高い経験となった。オープニングパーティーの席で、「この様な先生方とご一緒出来るなんて、なんと私は幸運な人間なのだろう。」と挨拶させていただいた。その後の歓談の際、「君の写真のスタイルはオーソドックスだね。」と言われたのを良く憶えている。この会話のお陰で僕は自分の写真のスタイルについて改めて考えることが多くなった。そこで、「私もそろそろアバンギャルドな作風に変えていく必要がありますか?」という疑問を大先輩の写真家や芸術家にお会いした都度問いかけた時期があった。すると、その質問に全員が首を横に振った。「君のスタイルをこのまま持続した方がいい・・。」 結局、ものを創ったり、写真を撮る人間にとって、オーソドックスか前衛かというのは表現方法という入れ物の問題であって、最も大切なのは、「何を撮ろうとしているのか」という中身なのだ、という答えが返ってきた。
では、写真を撮る時、中身、つまりテーマはどの様に紡ぎ出していけば良いのだろうか。写真家 安井仲治は、彼の写真展の冒頭でこう書いている。「今日、僕はこんな美しいものを見たんだ、ということを見る人に伝えれば良いのだ。そして、必要なのは眼の教養と敏感な感受性だ。」 僕はこの言葉に大いに揺さぶられた。こんなにも綺麗な夕焼けが広がっていた、こんなに洒落たカップルが公園にいた、こんな可愛い犬を連れた女の子とすれ違った、こんなに一生懸命生きているおばあちゃんを見かけた、世界でこんなことが起こっている・・・。これらを一枚一枚、大切に写真にすれば、自分の眼に根ざした立派な作品になるのではないか。ものごとを見てまず感動する。つまり自分の心が働く。そして、ものごとを正しく理解する知識、頭が必要になる。あとは、被写体として構図や光をどう決めるかという眼のセンス、すなわち写真的センスを発揮すればよいのだ。アンリ・カルティエ=ブレッソンは、写真とは「眼と頭と心」で撮るものだ、と言っているのがよく理解出来る。
”カルティエ=ブレッソンの 「chez lip」(リップにて)1968年“という作品がある。パリでのスナップ写真の一枚だ。カフェの店先、手前の椅子に座ったミニスカートの若い女性。その若い女性をとがめるように鋭く、冷たい視線を浴びせている年配の婦人。二人はそれぞれの手に今日の新聞を持っているという写真だ。この写真には解説が添えられていて、これが非常に興味深い。解説によると問題はこの新聞だ。一見、分別のありそうな年配の婦人が持っているのは、ゴシップ記事満載の大衆紙、一方のミニスカートの女性が手にしているのは、インテリが読む、クオリティー・ペーパー、「ル・モンド」なのだ。二紙の違いを見抜く知識がないと、この写真の深みを理解することは出来ない。カルティエ=ブレッソンの言う、頭、教養が問われるのだ。
さあ、心と頭と眼を養って一枚の写真をものにしようではないか。ここで日々の努力がものをいう。いままでどういう人生を送ってきたかが問われる。なんて写真とはスリリングなものだろう。言い方を変えれば、作品とは、作者の内面、つまり心の叫びや生き方、良心が正直に反映されるものであって欲しいと願っている。
■ハービー・山口写真展
『あの美しかった冬の光』
2008年2月1日(金)〜3月29日(土)
Blitz Gallery Art Photo Site Tokyo 13:00〜19:00 日曜・月曜休廊
www.artphoto-site.com/gallery.html